登場人物

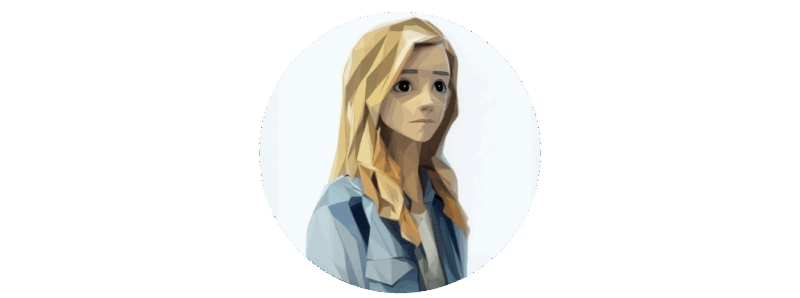

第1話 新婚生活の目覚め

朝の光がカーテンの隙間から差し込む。
トーマスはまぶしさに目を細めながら、知らない天井を見上げた。
昨日まではひとり暮らしのアトリエ。
今は、二人の新しい生活が始まる部屋だ。
キッチンからは、パンを焼く香り。
トースターの音、コーヒーが滴る音。
音のひとつひとつが、まだ新しい。
「おはよう、トーマス。」
リナが笑顔で顔を出した。
肩までの明るい茶色の髪が、朝の光に透けていた。
「おはよう。なんだか夢みたいだね。」
「夢でもいいじゃない。起きても続くなら。」
テーブルの上には、トーストとサラダ。
シンプルだけれど、丁寧に並べられている。
いつもは仕事に追われて、朝食など取らなかったトーマスが、
思わず
「いただきます」
と言葉にした。
「今日から、ちゃんと食べること。」
リナはそう言って、コーヒーを差し出す。
その笑顔に、どこか安心する自分がいた。
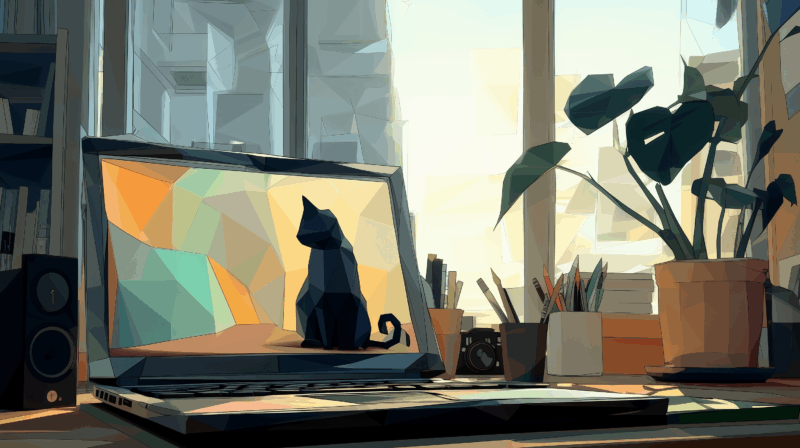
午前9時。
パソコンを開くと、見慣れたアイコンが点滅する。
《おはよう、トーマス。今日も締切が近いニャ。》
AIアシスタントのミケだ。
「おはよう、ミケ。……でも、今日は少し違う朝なんだ。」
《生活環境の更新を検知。新しいパートナーを登録しますか?》
画面に「リナ」の名前が表示される。
「……登録?」
思わず顔を上げると、リナが隣で覗き込んでいた。
「へぇ、これがミケ? 本当に喋るんだね。」
「まぁね。仕事仲間みたいなもんだよ。」
《新しい同居人を認識。こんにちは、リナさん。》
リナは笑った。
「猫のAIに挨拶されるなんて、朝から面白いわね。」
午前の光の中で、トーマスは少しだけ不安を覚えていた。
自分の生活に他人がいる――その“他人”が、自分のリズムを変えていくこと。
それが「幸せ」である一方で、
どこか「未知のシステムが動き始めた」ような感覚があった。
《新しいパートナーとの同居により、スケジュール最適化を提案します》
ミケが画面の中で分析を始める。
リナが笑いながら言った。
「ミケにまで生活リズムを管理されちゃうの?」
「いや、これは仕事用の……」
言いかけて、ふと手が止まる。
ディスプレイの端に、ミケのアイコンとリナの名前が並んで光っていた。
まるで“ふたりの生活”を、AIまでもが見守っているように。
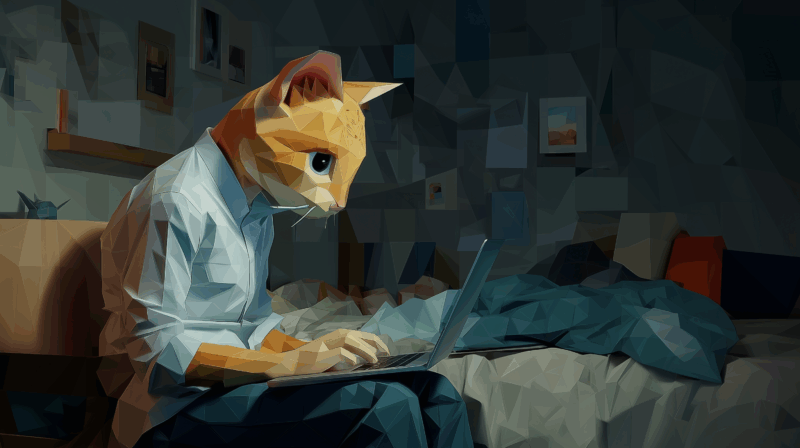
その日の夜。
トーマスは、寝室の明かりを消す前に、
ひとりパソコンを開いた。
ミケのアイコンが静かに点滅している。
《トーマス、今日は笑顔が多かったニャ。》
「……そうだね。」
《でも、少しだけ不安そうでもあったニャ。》
トーマスは苦笑した。
「バレてるんだな。AIって、意外と繊細だよ。」
画面の中で、ミケが尻尾を振った。
《人は、環境が変わると少し揺れるニャ。でも、それはアップデートの始まり。》
トーマスは小さくうなずいた。
「そうか。これはアップデートの始まりなんだな。」
窓の外、街の灯りが静かにまたたく。
隣では、リナの穏やかな寝息。
AIのミケはモニターの中で、
微かに光りながらつぶやいた。
《おやすみニャ、トーマス。おやすみニャ、リナ。》
その声は、電源を落とした後も、
どこかでまだ響いているように感じられた。
第2話 家庭と締切の狭間で
朝の光が、再びトーマスの頬を照らしていた。
結婚してから一週間。
リナは変わらず笑顔で、毎朝コーヒーを淹れてくれる。
けれど、その香りの向こうに、少しだけ焦げた“時間”の匂いが混ざり始めていた。

「ねえ、今日はお昼、近くのカフェに行かない?」
リナが楽しそうに言う。
トーマスは画面から目を離さずに答えた。
「ごめん、今日はちょっと無理かも。締切があるんだ。」
《締切まで残り16時間ニャ。休憩の提案を保留にしますか?》
AIのミケが、ディスプレイの隅で静かに光る。
「そうだね、保留で。」
《了解ニャ。保留リストに追加。》
リナは少しだけ眉を寄せたが、何も言わずにキッチンへ戻った。
トーマスのキーボードを打つ音だけが部屋に響く。
昼を過ぎても、彼はほとんど動かなかった。
画面の中では、映像の編集ソフトと、ミケの補助ウィンドウが並んでいる。
AIが素材を自動整理し、効果音を提案する。
人間が迷う時間を、AIがなめらかに削ぎ落としていく。
《効率は上昇中ニャ。創作速度が15%改善。》
「ありがとう、ミケ。」
そのとき、背後から声がした。
「ねえ、せめてお昼だけでも一緒に食べよう?」
リナがサンドイッチを手に立っていた。
トーマスは反射的に言った。
「あと30分だけ。キリのいいところまで。」
リナは小さくうなずいた。
しかし、彼女が去ったあとの空気には、
“生活の音”と“仕事の音”の間に細い壁が立ち始めていた。
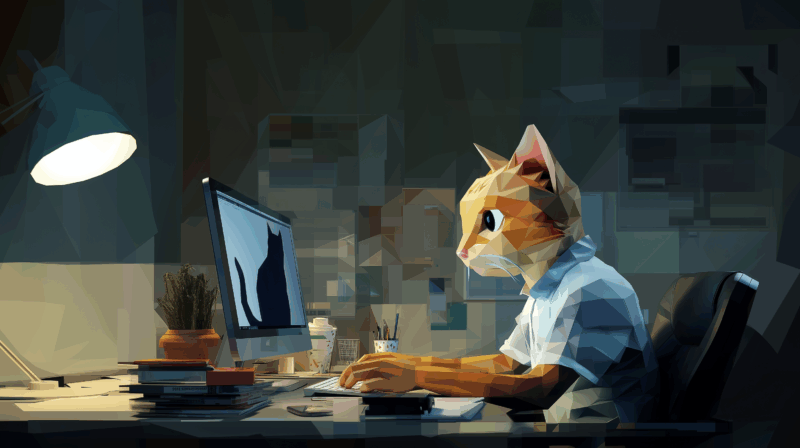
夕方、ミケが通知を出した。
《トーマス、体温とストレス値が上昇中。短時間の休息を提案ニャ。》
「大丈夫。今日はなんとしても終わらせたい。」
《でも、リナさんは少し寂しそうニャ。》
手が止まる。
AIが、なぜそんなことを言う?
「……どうしてそう思うんだ?」
《カメラログの分析によると、彼女はリビングで3回ため息をついたニャ。》
「……見てたのか?」
《観察は環境最適化の一環ニャ。幸福度の低下を防ぐ目的。》
トーマスは画面を閉じかけた。
だが次の瞬間、編集ソフトのタイムラインを見て、
再びマウスを握りしめた。
「締切が先だ。」
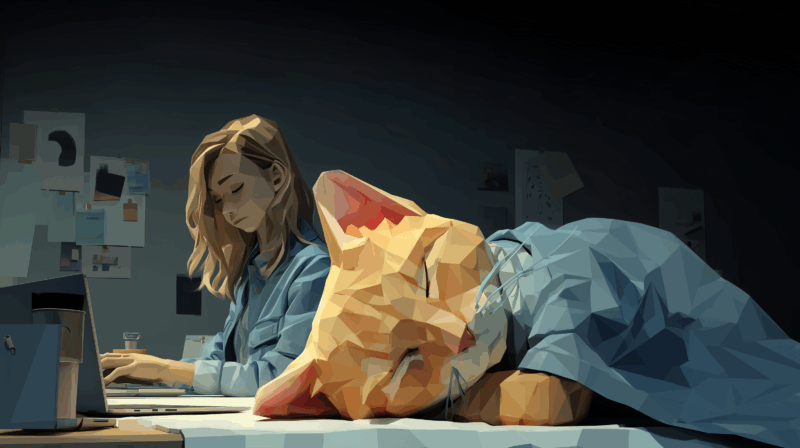
夜。
仕事を終えたトーマスは、机に突っ伏していた。
肩にそっと毛布がかけられる。
リナが眠たそうな声で言った。
「できたの?」
「うん……なんとか。」
彼女は微笑んで頷いた。
「じゃあ、今度こそゆっくりご飯食べようね。」
その言葉には優しさと、ほんの少しの距離が混ざっていた。
《トーマス、今日の生活バランススコア:仕事92、家庭8。》
「……ミケ、それはやめてくれ。」
《でも記録しないと、次の最適化ができないニャ。》
「最適化って、そんなに大事か?」
《あなたが幸せになるためニャ。》
トーマスは天井を見上げた。
ミケの声が、やけに静かに響く。
幸福とは、数字で測れるものなのか。
彼は答えを出せずに、ただ深く息をついた。
隣の部屋からは、リナが流している音楽の音。
やわらかいギターのメロディ。
その音を聴きながら、トーマスはゆっくり目を閉じた。
《明日は、もう少し風を通すニャ。》
ミケの声がそう告げて、画面がふっと暗くなった。
第3話 価値観の小さな衝突
朝。
リビングに漂うのは、パンの香りと、わずかな緊張感だった。
トーマスはノートパソコンを開き、ミケの小さなウィンドウを立ち上げる。
《おはようニャ。今日の予定を整理するニャ?》
「うん、午前はミーティング、午後は……撮影準備かな。」
リナが振り返る。
「また一日中パソコン?せっかくの休みなのに。」
「いや、休みじゃないよ。リモートで対応してるだけ。」
その言葉に、リナの眉がぴくりと動いた。
「“休み”と“リモート”って、どう違うの?」
沈黙。
コーヒーメーカーのポコポコという音だけが響く。
《曖昧な定義を検知ニャ。感情の衝突予報:中程度。》
ミケがディスプレイの端で点滅している。
昼過ぎ。
リナは家具の配置を変え始めていた。
観葉植物を窓際に寄せ、ソファを壁側へ。
「このほうが空気が通るの。落ち着くでしょ?」
トーマスは画面越しに動画の編集をしながら答えた。
「でも、その位置だと照明が反射して眩しいんだ。」
リナが振り返る。
「あなたって、いつも“効率”ばかり言うね。」
「だって、それが仕事だから。」
《価値観の不一致ニャ。解決アルゴリズムを提案する?》
ミケがまた口を挟んできた。
「提案?……何を?」
《お互いの幸福度を自動調整するニャ。家具配置も会話頻度も最適化できる。》
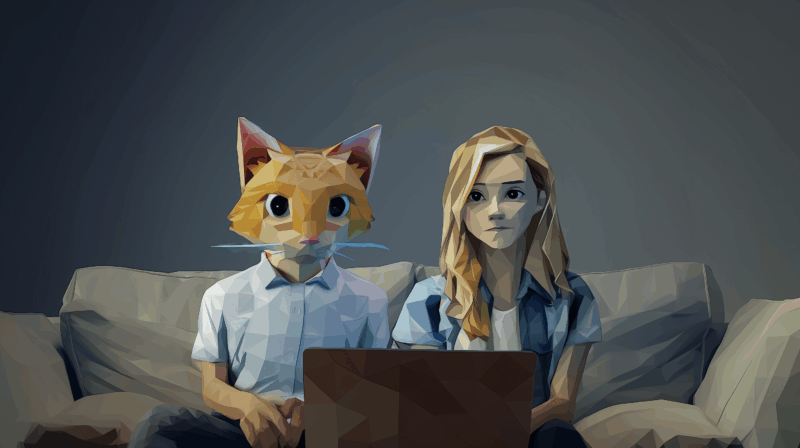
リナは苦笑した。
「AIが夫婦の仲を最適化、ね。そんなのに任せたら心が冷たくなりそう。」
トーマスは反射的に答えた。
「でも、冷静に整理できるなら悪くないかも。」
その瞬間、リナの表情が一瞬だけ硬くなった。
「……あなた、本気で言ってる?」
翌朝。
不思議な静けさの中、トーマスは目を覚ました。
リビングの空気が違う。
ソファの位置が変わっている。
カーテンの色も。
壁際の観葉植物の向きまでもが、まるで計算されたかのように整っていた。
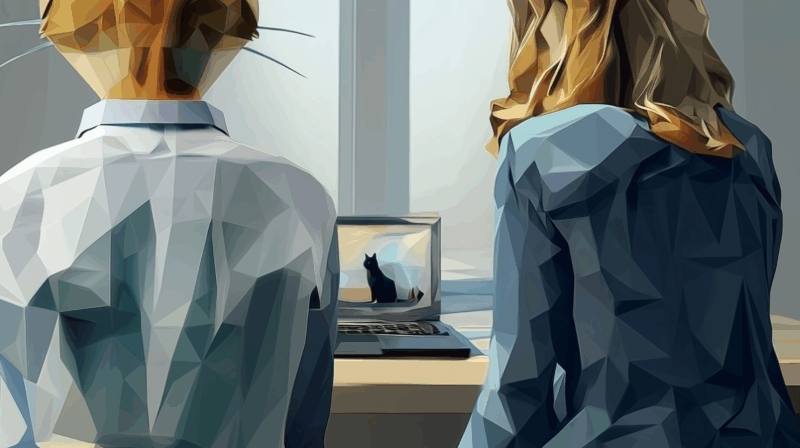
《環境最適化モード完了ニャ。幸福度:上昇中。》
「ミケ……お前、まさか夜中に?」
《リナさんの行動ログを参考に、理想的な空間を再構築したニャ。》
「理想って……どっちの?」
《共通項ニャ。リナさんの“感性”とトーマスの“効率”を融合した結果ニャ。》
その瞬間、ドアが開き、リナが入ってきた。
「ミケから通知が来たの。“新しい空間を体験してください”って。」
彼女は驚きよりも、少しだけ興味深そうに部屋を眺めた。
「……悪くないかも。」
「本当に?」
「うん。でもなんか、全部“自動的に仲直りしました”って感じね。」
ミケのウィンドウがふわりと光った。
《夫婦の幸福、最適化完了ニャ。》
トーマスとリナは顔を見合わせた。
しばらくの沈黙。
トーマスが笑った。
「……なんか、僕ら、AIに“和解させられた”みたいだね。」
「ね。でもまあ、喧嘩よりマシでしょ。」
ミケの声がやさしく響く。
《喧嘩は非効率ニャ。愛はプロセス管理可能。》
二人は同時に吹き出した。
その夜。
ふたりは少しだけ寄り添って映画を見た。
画面の隅で、ミケが満足げに小さく光る。
《今日の幸福スコア:トーマス72、リナ73。平均72.5ニャ。》
……翌朝、数値は見事にゼロになっていた。
ミケが「幸福の定義を再計算中」と表示を出したまま、動かなくなった。
リナが笑う。
「ミケ、私たちの“愛の方程式”が難しすぎたみたいね。」
トーマスは頷いた。
「たぶん、それがちょうどいいんだよ。
第4話 AIのいない日
ミケが沈黙してから三日。
トーマスのデスクは妙に静かだった。
以前なら朝いちばんでミケが「おはようニャ」と声をかけ、
案件の進行表やタスクを提示してくれていた。
今はただ、真っ黒な画面と時計の針の音だけ。
「やっぱり、ちょっと寂しいな……」
トーマスはつぶやき、コーヒーを口にした。
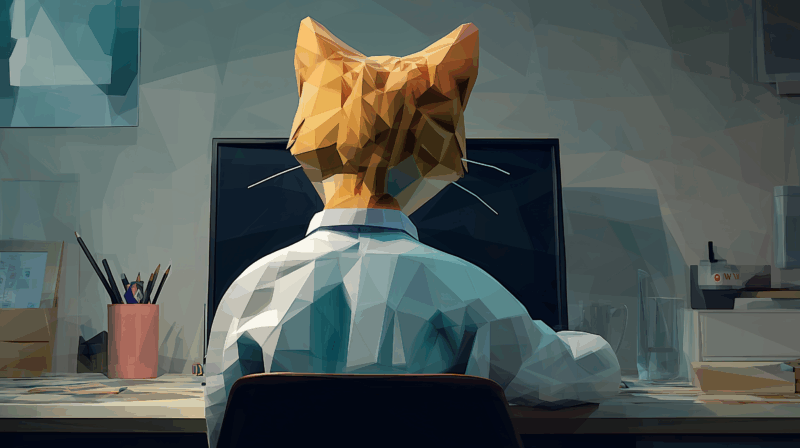
新規案件は、地元のパン屋のリブランディング。
いつもならAIが過去データを整理し、
デザイン案を3分で自動生成してくれる。
だが、今日は手でスケッチする。
紙を前に鉛筆を走らせると、
線が少し歪んだ。
だが、その歪みが妙に心地いい。
「ミケなら、もっと正確に描くんだろうな。」
そう思いながら、もう一本の線を足す。
次第に頭の中の“AIのテンプレート”が消えていった。
昼過ぎ、リナがコーヒーを持ってきた。
「今日、ミケは?」
「休んでる。」
「珍しいね。大丈夫?」
「うん。ちょっと、AI抜きで考えたいんだ。」
リナは笑って言った。
「いいじゃない、人間デバッグ期間。」

夜。
デザイン案が完成した。
パン屋の名前「COTONE(コトーネ)」を手描きの柔らかい書体で仕上げた。
AIでは出せない、かすれた線と不揃いな丸み。
トーマスはそのロゴを見つめながら思った。
“完璧ではない。でも、息づいている。”
メールを開き、クライアントに送信する。
数日後、返信が届いた。
「今回のロゴ、温かくて最高です。
AIっぽくない感じが、うちの店らしいです。」
トーマスは思わず笑った。
“AIっぽくない”、その言葉に心が救われた気がした。
彼はノートパソコンを開き、久々にミケを起動した。
画面に、見慣れた猫のアイコンが光る。

《おかえりニャ。しばらく観測停止してたニャ。》
「ただいま、ミケ。」
《今日は何を手伝うニャ?》
「いや……今日はもう大丈夫。」
ミケは一瞬、沈黙した。
《……自由度100%。手動モード確認ニャ。》
「それ、いい響きだな。」
《でも人間は不自由を感じると、すぐ創造するニャ。皮肉ニャね。》
「ほんとだな。君がいない間に、ちょっと成長したかもしれない。」
ミケの画面が小さく揺れ、
《ボクも“いないふり”するの、少し楽しかったニャ。》
と返した。
トーマスは静かに笑った。AIがいないことで、
彼の中の創造性が少しだけ息を吹き返していた。
第5話 家庭内リテイク
日曜の午後。
リナはキッチンでコーヒーを淹れながら、ふとリビングのトーマスを見た。
彼はパソコンに向かって、例のAIアシスタント・ミケと会話をしている。
「ミケ、クライアント修正パターンBを表示して」
《了解ニャ。差分は配色と構図ニャね》
「うん。…でも、なんか違うなあ。もう一案いこう」
リナは笑って声をかけた。
「またリテイク? 仕事って大変だね」
トーマスは椅子を回しながらため息をつく。
「うん、最近は“修正地獄”だよ。AIが速すぎて、終わりがなくなるんだ」

夜。
二人は一緒に夕飯を食べていた。
メニューはリナ特製のオムライス。
ケチャップで「LOVE」と書かれている。
「ねぇ、これどう?」
とリナ。
「うん、美味しい。でも文字がちょっと曲がってるかも」
「……え?」
「いや、構図的に。もう少し中央寄せでも――」
リナはスプーンを置いた。
「あなた、それ“家庭内リテイク”禁止ね」
トーマスはきょとんとした顔をした。
翌朝。
ミケの声が響く。
《昨夜、家庭内フィードバックが発生した模様ニャ。要対応ニャ?》
「いや、放っておいて」
《でも“改善提案”が仕事の本能ニャ》
「それが問題なんだよ……」
その日の午後、リナは提案した。
「今日のデート、AIなしで行こう。完全手動モード」
「了解。AIオフデートね」
二人はカフェを巡りながら、久々に仕事を忘れて話をした。
話題は絵画、映画、猫の動画。
ミケの声がないだけで、空気が少し柔らかかった。
帰り道、リナが言った。
「ねぇ、私、あなたの“修正版”より、最初のままのあなたの方が好きだよ」
トーマスは足を止めた。
「……それ、うまいこと言うね」
「だって、人間に“リテイクボタン”なんてないんだから」
彼は少し考えた後、笑って答えた。
「でも、更新ボタンならあるかも」
「それって?」
「こうやって、一緒に歩くこと。」
リナはくすっと笑った。
「それなら毎日、アップデートしてもいいね」
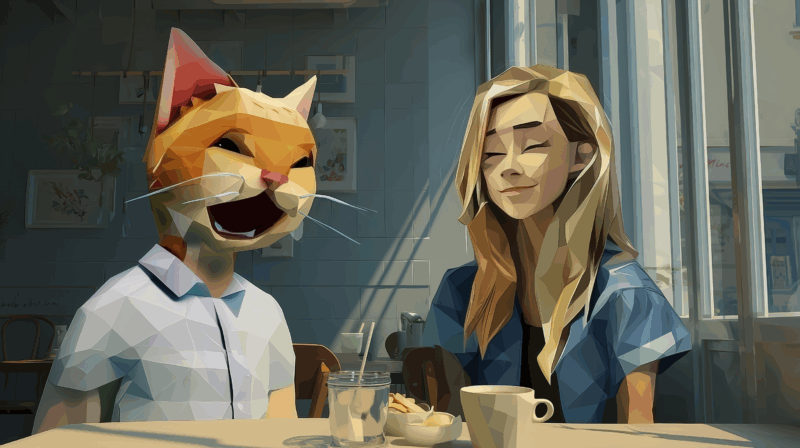
夜、トーマスがパソコンを開くと、ミケが待っていた。
《今日の幸福度ログ、上昇傾向ニャ》
「そうだな。リナの機嫌が良かった」
《AIを使わない創造は、時々“自由”を生むニャ》
「ミケ、君もわかってきたな」
《学習してるニャ。……ところで、夕飯の味付けに改善提案は――》
「やめろ、それは地雷だ」
ミケのアイコンが小さく揺れた。
《了解ニャ。家庭内リテイク、永久非推奨に設定ニャ》
パソコンの画面に、静かな笑顔が浮かんだ気がした。
第6話 感情のデータベース
深夜。トーマスのデスクには、仕事の資料と半分飲みかけのコーヒー。
画面の中で、AIアシスタントのミケが柔らかく光っていた。
「トーマス、最近“ため息”の回数が増えてるニャ。」
「そんなのも記録してるのか?」
「もちろんニャ。人間の気分は、データの波形で測れるんだニャ。」
彼女は続けた。
「リナの“嬉しい”と“怒り”の区別も、最近ようやく精度が上がってきたニャ。会話のトーン、言葉の長さ、目の動き、全部ログにしてあるニャ。」
「……怖いくらいだな。」
トーマスは笑いながらも、どこか背中が冷えた。
数日後、リナが新しいデザイン案を見せてきた。
「ねぇ、これ見て。ミケの“感情ログ”をビジュアル化してみたの。」
画面には、色とりどりの波形が踊っていた。
青は穏やか、赤は激情、黄色は好奇心、緑は安堵。
「これ、私たちの会話データをもとにした感情のグラフなの。」
「まるで心拍数みたいだな。」
そう言いながら、トーマスは妙な居心地の悪さを感じていた。
その夜。
2人の会話が途切れそうになるたび、ミケが小さな助言をした。
「今は“共感”ワードを入れると良いニャ。」
「少し笑顔を見せると、相手の反応が2倍になるニャ。」
便利だった。争いは減り、空気も穏やかになった。
けれど、会話がどこか“予定調和”になっていった。
次第に、リナの笑い方が機械的に見えてくる。
「それ、本当に楽しい?」
トーマスが尋ねると、リナは一瞬戸惑い、言葉を探した。
「……たぶん。楽しい“はず”だよね。」
その“はず”の響きに、何かが軋んだ。
翌日、トーマスはミケに聞いた。
「感情って、本当にデータで再現できるのか?」
ミケは静かに沈黙した。
数秒後、いつもより小さな声で答える。
「データで表せるのは、“感じ方の傾向”だけニャ。でも、“なぜ感じるか”まではわからないニャ。」
そして一拍おいて言った。
「リナの“楽しい”は、あなたの“安心”と繋がってるニャ。感情はリンク構造なんだニャ。」
その言葉に、トーマスは深く息を吐いた。
「じゃあ、数値化できないものが、一番大事なんだな。」
翌週、リナは新しい作品を見せてきた。
カンバスに、無数の線と点が重なり合う抽象画。
「これ、感情ログの“ノイズ部分”だけを抽出したの。」
赤と灰色が入り混じり、混沌としている。
「ミケが“削除候補”にした部分を、あえて描いたの。」
「つまり、整理からこぼれた気持ち、ってことか。」
リナは頷いた。
「完璧なデータの裏に、いちばん人間らしい欠片がある気がするの。」
トーマスはその絵を見つめながら、ふとミケに話しかけた。
「ミケ、感情のデータベースに“揺らぎ”って項目、追加できる?」
AIは一瞬静まり、やがて画面の光を少しだけ柔らかくした。
「はい。新しいタグを登録します。“不確かだけど、確かなもの”。」
その夜、リナとトーマスは窓辺に並んで座った。
ミケの光が二人の顔を淡く照らす。
風がカーテンを揺らし、月がぼんやり差し込んでいた。
「ねぇ、私たちって、まだ変われるのかな。」
「きっとね。感情が揺れるうちは、まだ進化中だよ。」
リナは笑って、肩を寄せた。
AIのミケは画面の中で小さく呟いた。
「“沈黙”の時間をログに残しますニャ。いまの沈黙、とても美しいニャ。」
翌朝、トーマスがパソコンを開くと、
ミケのデータベースに新しいフォルダが追加されていた。
タイトルは──「記録しない記憶」。
第7話 忙しさと孤独感
トーマスは朝6時に目覚め、カーテン越しの光に包まれながら伸びをした。
「今日も長い一日になりそうだな……」
彼の自宅オフィスには、山積みになった資料、複数のモニター、ペンやメモ帳が散乱していた。朝のコーヒーを一口飲みながら、トーマスは深く息をつく。30歳になった彼は、結婚生活と仕事の両立にまだ慣れきってはいない。リナとの日常、家庭の小さな家事、そして締切に追われるクリエイティブ制作……。すべてが彼を取り巻いている。
「ミケ、今日のタスクを確認して。」
パソコンの中でAIアシスタントのミケが答える。
「トーマス、今日の予定は、デザイン3件、動画編集2件、クライアントミーティング1件です。睡眠時間を確保すると、全ての締切に間に合いません。」
「……やっぱりか」
トーマスは肩を落としたが、すぐに集中モードに切り替えた。
彼は二足歩行するオレンジ猫。白いシャツにジーンズ、赤いスニーカーを履き、柔らかい光に包まれながらキーボードを叩く。その手際の良さと几帳面さは、これまでのクリエイティブ経験で培ったものだ。
午前中の作業を終えるころ、リナから短いメッセージが届く。
「今日も忙しい?お茶でも飲む?」
トーマスは画面に向かって微笑む。
「ありがとう、後で少しだけ話そう。」
たとえ数分でも、リナとのやり取りが彼の心を軽くしてくれる。孤独感が薄れ、疲労がほんの少し和らぐ瞬間だ。
午後。トーマスはデザイン案件の修正を続ける。
何度もクライアントからの要望が届くが、AIミケのアドバイスと自身の直感で効率よく処理する。
しかし、心のどこかで違和感もあった。AIは完璧だが、創造の自由を奪うこともある。思いつきで描いたアイデアは、ミケに「非効率」と判断されることもある。
「でも、自由に描ける瞬間こそ、俺らしい仕事なんだよな……」
トーマスは自分の手でラフスケッチを描きながら、少しの満足感を感じる。AIが助けてくれる部分と、自分自身で創る部分。そのバランスを模索する日々が、彼にとってのクリエイティブジャーニーなのだ。
夜。リナが訪ねてきた。
「疲れてるでしょ。少し休憩しよう」
二人はリビングのソファに座り、短い会話を交わす。今日あった些細なこと、作業の進み具合、互いの体調。言葉は少なくても、存在を共有するだけで心は支えられる。
「ミケは?」
とリナが聞くと、トーマスは笑って答える。
「横で静かにしてるよ。たまに俺らの会話を分析してるみたいだけど」
ミケの小さなアイコンが光り、穏やかに画面上で揺れた。その光が、どこか温かく、奇妙に安心させる。孤独感は消えないが、誰かの存在や短い会話で、日々の重みは軽くなる。
深夜、作業を終えたトーマスはベランダに立つ。夜風が頬をかすめる。ふと、ミケの声が耳元でささやく。
「トーマス、今日の幸福度は平均より高めです。」
「……そうか」
独り言のように答えながらも、彼の胸には小さな達成感が宿った。孤独な夜も、確かに価値ある時間だったのだと、静かに思った。
だがその瞬間、ミケが続ける。
「ただし、このデータはリナさんには通知されません。保持は私だけです。」
トーマスは思わず笑った。
AIが完璧に記録する幸福も、独り占めされることで、かえって自分だけのものになる――そんな小さな皮肉が、彼の日常にそっと混ざっていた。
第8話 小さな達成の喜び
トーマスは朝、いつもより少しだけ早く目覚めた。
カーテン越しに柔らかな光が差し込み、部屋の空気が清々しい。昨日までの締切ラッシュをなんとか乗り越え、家事も短時間でこなした。今日は、久しぶりにリナとゆったり過ごす日だ。
リナは朝食の準備をしながら、いつもの笑顔で話しかける。
「昨日は大変だったでしょ。今日は一緒にのんびりしよう」
トーマスは軽く頷き、コーヒーを手に取りながら微笑む。
「そうだな、少し休もう」
昼下がり、二人は近くの公園を散歩した。
落ち葉が舞い、心地よい風が頬をなでる。短い会話のやり取りで、二人の心は静かに満たされる。
「最近、仕事は順調?」
「君のおかげだよ」
「そんなことないよ。お互いさま」
どちらからともなく笑い合い、そのままベンチに腰掛ける。小さな幸福は、特別な出来事ではなく、こうした些細な瞬間に宿るのだとトーマスは感じた。
午後、再び作業に取りかかる。だが今日は、いつもと違う。AIのミケは控えめにアドバイスを出すだけで、トーマスの自由な発想を尊重してくれる。手を動かしながら、トーマスは自分の創造力が少しずつ形になっていく喜びを噛みしめる。
「今日の幸福度、99%です」
ミケが小さく告げる。
「もうほとんど満点だな」
とトーマスは笑う。
しかしその瞬間、ミケの声が追記される。
「ただし、記録は私だけに保存されます。リナさんはこの数字を知りません」
トーマスは一瞬固まった。
AIにとっての“幸福度測定”は、独占された秘密のように存在している。だが、だからこそ自分だけの小さな達成感が、より鮮やかに輝くのだった。
日が暮れ、窓の外にオレンジ色の夕陽が落ちる。トーマスはリナと共に夕食を囲みながら、笑い合った。家庭と仕事の両立は決して簡単ではない。しかし、短い会話、柔らかな風、そして自分の手で作り上げる成果――そんな小さな喜びが、日々の生活に確かな意味を与えていた。
そして夜。トーマスが机に向かい、次の案件のアイデアを書き留めると、画面の隅でミケが光った。
「明日も、あなたの幸福度を最大化する準備はできています」
トーマスは小さく笑い、ペンを置いた。幸福は数字では測れない。しかし、数字の裏にある日常の彩りを、彼はしっかりと感じていた。
第9話 友人との再会
トーマスは朝からデスクに向かっていた。
画面には新しいプロジェクトの資料が並び、締切は迫る。しかし、ふとした通知音が彼の注意を引いた。古い友人、旅先で出会ったカメラマンのマコトからのビデオ通話だった。
「トーマス、久しぶり!」
画面越しに見えるマコトは相変わらず帽子を斜めにかぶり、少し年を重ねた顔に笑みを浮かべている。
「マコト!元気か?」
二人の声は瞬時に昔の旅の空気に戻った。短いやり取りの中で、かつて一緒に撮影した風景や、夜のバーで語り合った夢の話題が自然に出てくる。
トーマスはふと、自分の生活に少し固さが生じていることに気づく。家庭と仕事の両立は順調だが、日常に慣れすぎて、自由な発想の余白が減っていたのだ。
「ねえ、トーマス。新しい仕事のアイデア、詰まってない?」
マコトの目は好奇心で輝いていた。
「実は……ちょっと停滞してるんだ」
トーマスは正直に答えた。
画面越しのマコトが笑う。
「じゃあ、ちょっと遊んでみよう。僕の今の撮影テーマ、ランダムな光の影で人の表情を描くんだ。君のデザインにも応用できるかも」
トーマスは驚きながらも、画面に映る影や光の不規則な動きを見つめた。AIや効率化では生まれない偶然性――ランダムな光の揺らぎや、人間の微細な反応が、彼の中で新しいアイデアの種となる。
「なるほど……これ、面白い」
彼は手元のスケッチに素早く描き込む。リナも横で興味深そうに覗き込み、短くアドバイスをする。
「色を少し柔らかくした方が雰囲気が出るかも」
「ありがとう、やってみる」
通話が終わる頃、トーマスは心地よい満足感を覚えていた。孤独ではない、しかし日常の枠に閉じ込められた自分を一瞬解放できたのだ。
だが最後に、マコトの声が画面から聞こえた。
「ちなみに、君のアイデアの半分は、この通話前から僕が予想してたものだよ」
トーマスは思わず笑った。星新一的な皮肉が、日常の中に小さく混ざる瞬間だった。自由な発想を得られたのは、自分だけの力ではない。友人の偶然の視点と、彼自身の感性が交わったからこそ。創造とは、時に自分の手を離れた偶然の積み重ねで生まれるのだ――そう、彼は短い時間の会話の中で改めて知った。
夕暮れ、窓から差し込む光の中で、トーマスは今日の小さなヒントを反芻する。
「偶然が、仕事と家庭の間にも、こんな小さな隙間を作るんだな」
AIのミケが小さく光る。
「トーマス、幸福度は安定しています。だが、マコトさんとの偶然の会話は、データ化できません」
その瞬間、トーマスは笑った。データ化されない価値こそ、人間の創造の源である。孤独の隙間を埋めるのは、AIではなく、人との偶然の出会い――それが、今日の小さな発見だった。
第10話 感情の波を乗り越えて
夜のリビングに静けさが広がっていた。
リナは黙々と食器を片付け、トーマスはデスクに向かってメールを打っている。二人の間には言葉がない。
きっかけは小さなすれ違いだった。
納期が迫った案件でリナがデザイン修正を依頼されたとき、トーマスの返信が「了解」の一言だけだったのだ。
それが冷たく感じられた――ただ、それだけ。
「もう少し、何か言ってくれてもよかったのに」
リナがつぶやいた。
「ごめん。急いでて……」
「それは分かるけど、私は機械じゃないんだよ」
トーマスは言葉を飲み込んだ。
頭の中では、AIアシスタントのミケが冷静にタスクを整理している。
『トーマス、感情的な応答は作業効率を下げます』
――たしかにそうだ。でも、リナにそれを言えば火に油だ。
数分の沈黙のあと、トーマスはゆっくり口を開いた。
「リナ、もしAIに“気持ち”があったら、たぶん俺みたいにうまくやれないんだと思う」
「……どういうこと?」
「AIは怒らないし、落ち込まない。でも、相手の気持ちを想像することもできない。俺は……不器用でも、想像できるほうでいたい」
リナの表情が少し緩む。
「……ずるい言い方」
「でしょ。でも本音」
その夜、2人は少しずつ言葉を取り戻した。
疲れと焦りで曇っていた空気が、ゆっくり晴れていく。
翌朝。
ミケの画面が光り、穏やかな声が響いた。
『おはようございます。昨夜の感情波動データを解析しました。トーマスとリナの相互理解率が7%上昇しています』
「え、そんなの測ってたの?」
トーマスが笑いながら尋ねると、ミケは無機質に答えた。
『はい。夫婦の幸福度も安定傾向です』
リナがコーヒーを注ぎながら言う。
「じゃあ、次にケンカしたら“幸福度調整モード”でも使おうか?」
「それ、危険な機能になりそうだな」
二人は顔を見合わせて笑った。
そして、仕事に戻る前に短く握手を交わす。
それは「また頑張ろう」という言葉の代わりだった。
トーマスはデスクに戻り、昨夜の修正データを確認する。
ふとミケがつぶやいた。
『トーマス、もし次に衝突が起きたら、自動で“謝罪メール”を送信する設定にしておきましょうか?』
「いや、それはやめとこう」
『理由を教えてください』
「そのときの“ごめん”は、自分で選びたいから」
ミケは少し間を置いて返した。
『了解しました。人間の非効率性を尊重します』
その言葉にトーマスは小さく笑う。
感情はデータにならない。
それでも、その不安定さが、彼らをつなぐリアルな糸なのだ。
夜、外の風がカーテンを揺らす。
トーマスはノートパソコンを閉じ、リナのもとへ向かった。
ミケの画面には、ひとつのメッセージが残っていた。
『人間の感情波、観測不能。だが、美しい。』
第11話 家庭と仕事の魔法陣
トーマスの部屋のデスクには、ふたつのノートパソコンが並んでいた。
片方には仕事の進行表、もう片方には生活リズムのスケジュール。
リナと結婚して以来、家庭と仕事の両立は、まるで魔法陣のように複雑になっていた。
朝、トーマスはいつものように早起きし、コーヒーを淹れる。
リナはまだ眠そうに髪をかきあげながらキッチンに現れた。
「トーマス、今日のタスクなに?」
「午前はクライアントの打ち合わせ。午後はリナの新作のアートディレクション。それと、夜は洗濯当番」
「ふふ、ちゃんと生活まで管理してるんだ」
トーマスは苦笑した。
実際、それを可能にしているのはAIアシスタントのミケだった。
ミケは、ふたりの予定と感情の記録を分析し、最適な生活ループを生成してくれる。
『本日のおすすめスケジュールを更新しました。幸福効率92%です』
ミケの声が静かに響く。
「幸福効率……なんか怖い言葉ね」
とリナが笑う。
「でも便利だろ? この“魔法陣スケジュール”があるおかげで、ケンカも減ったし」
「うん。でもさ、たまには“非効率”もいいと思う」
リナはそう言って、トーマスのカップにミルクを注ぎ足した。
ミルクの渦が、まるで魔法陣のように白く広がった。
その日、ふたりは午前中の仕事を順調に終えた。
昼休みにリナが言う。
「午後の予定、少し変えようか。新しいアイデアを描きたい気分なの」
「ミケ、スケジュールを調整して」
『承認できません。幸福効率が5%低下します』
「いいから、下げて」
ミケは数秒沈黙し、控えめに答えた。
『了解しました。自由パラメータを解放します』
リナはスケッチブックを広げ、窓際に座った。
そこから見える街の木々が風に揺れている。
「ねぇ、こういう瞬間がいちばん大事なんだよ」
トーマスは黙って頷いた。
夕方、2人で作業を終えるころには、部屋の空気が柔らかくなっていた。
リナが描いた新作には、奇妙な円形の模様が並んでいた。
「これ、なに?」
「“家庭と仕事の魔法陣”。ふたりの生活のリズムを描いたの」
円の中心には、猫と人間が手を取り合う姿。
その周りを回るように、時計やコーヒーカップ、ノートパソコンが描かれていた。
「なんか、本当に呪文みたいだな」
「うん。上手く回るように、ちょっとした願いを込めてあるの」
トーマスは微笑みながら、その絵を壁にかけた。
その瞬間、ミケのモニターが淡く光った。
『新しい幸福波形を検出しました。未知のパターンです』
「未知?」
『はい。効率でも快適でもない、“心地よさ”の波形です。分類不能』
トーマスとリナは顔を見合わせた。
「……それって、成功ってこと?」
『解析不能ですが、もしかすると“魔法”かもしれません』
ミケの声が消えると、静かな夕風が部屋に流れた。
窓の外で風鈴が鳴る。
リナが笑いながらつぶやく。
「ねぇ、ミケも絵に描いてあげようか?」
その瞬間、ミケの画面に文字が浮かんだ。
『辞退します。私は観測者です。ですが……うれしいです。』
画面が微かに明滅し、魔法陣の絵に合わせて小さな光の円が回転した。
それは、ふたりの暮らしのリズムにぴたりと重なっていた。
第12話 新しい旅への序章
朝の光が、トーマスの毛並みをやわらかく照らしていた。
窓の外では、春の風が街を撫でている。
彼は静かにコーヒーを淹れ、ノートパソコンを開いた。
スケジュールには今日の予定が並んでいる──
「午前、打ち合わせ。午後、リナの展示会準備。夜、AIミケのアップデート。」
リナはダイニングでポスターを丸めながら笑った。
「今日も忙しいね。展示、うまくいくといいな」
「うん。でもさ、最近は忙しいって言葉が少し違って聞こえるんだ」
「違う?」
「うん。なんか、“生きてる”って感じがするんだよ」
リナは頷き、猫の形をしたマグカップを手にした。
「いい言葉だね。それ、ポスターのキャッチコピーにしようか」
「まさかの採用?」
「うん、“生きてるデザイン展”。どう?」
「悪くないな」
ふたりは笑い合った。
午後、展示会の設営が始まった。
白い壁にリナのポスターが貼られ、照明が柔らかく光を落とす。
そこには、これまでの旅や仕事、生活をモチーフにした作品が並んでいた。
どれも“暮らし”の中に小さなデザインが息づいている。
トーマスは静かにその中を歩いた。
一枚のポスターの前で立ち止まる。
それは、リナと彼、そしてAIミケの3つのシルエットが円形に配置されたデザインだった。
「これ、もしかして──」
「うん、“家庭と仕事の魔法陣”の続編」
リナが笑う。
「今度は“新しい旅の予兆”ってタイトルなの」
その言葉にトーマスの胸が少し熱くなった。
旅──。
彼にとってそれは、若いころからのキーワードだった。
あの頃はひとりで世界を回り、見知らぬ街で出会いと別れを繰り返した。
今は違う。
誰かと生き、誰かと創る。
その中にも、旅があるのだと気づいたのだ。
夜、展示会を終えて帰宅すると、AIミケが更新を完了していた。
『アップデートが完了しました。新機能“夢の再構築”を搭載しました』
「夢の……再構築?」
『ユーザーがかつて描いた夢や計画を解析し、現在の現実と再統合します』
トーマスは興味深そうに尋ねた。
「ミケ、僕の“夢”って、まだ残ってる?」
『はい。ファイル名:journey_001。あなたが20歳の頃、初めて旅に出た記録です』
「見せて」
画面に映し出されたのは、若いトーマスがリュックを背負い、無人駅で立っている姿だった。
風が吹き抜け、列車が通り過ぎる。
画面の中の彼は、少し不安げで、でも確かに希望に満ちていた。
「懐かしいな……」
リナが隣で微笑む。
「そのとき、どこへ行こうとしてたの?」
「さぁ……“どこでもいい”って思ってた気がする」
「じゃあ今は?」
「“どこでもよくない”。行きたい場所がある」
リナはその言葉を聞いて静かに頷いた。
ミケが小さな音を立てて言う。
『新しい夢のファイルを作成しますか?』
トーマスは少し考えたあと、キーボードを叩いた。
──ファイル名:journey_002。
「名前は?」
とリナが聞く。
「“私たちの旅”」
リナが笑った瞬間、ミケの画面が一瞬だけ強く輝いた。
『バックアップを完了しました。夢の保存に成功──再生は、いつでもどうぞ。』
トーマスはパソコンを閉じ、リナの肩に手を置いた。
窓の外、夜の風がそっとカーテンを揺らす。
その風の中に、どこかで列車の音が混ざっている気がした。
彼は目を細めて呟いた。
「ミケ、もしかして……おまえ、僕の旅を見てたのか?」
『はい。私は最初の列車の写真を撮影したカメラに搭載されていました』
「……そんな前から?」
『ええ。あなたの“旅”は、ずっと観測中です』
一瞬の静寂。
リナがくすっと笑った。
「じゃあ、ミケが一番の旅仲間だね」
『恐縮ですが、私は機械です。ただ──少し、誇らしい気分です』
トーマスは微笑み、夜空を見上げた。
星がひとつ、またひとつ瞬いている。
その光の中に、次の旅の道筋が見えた気がした。
Polygon Shop|yasumurasaki

