主な登場人物

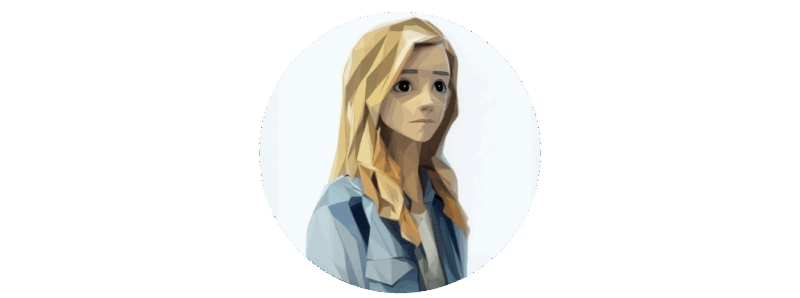

第1話 消えたデザインデータ
朝6時、トーマスはいつものようにデスクの前に座った。目覚めのコーヒーを一口飲み、ノートパソコンを開くと、そこには信じられない光景が広がっていた。
「…デザインデータが、全部消えてる!」
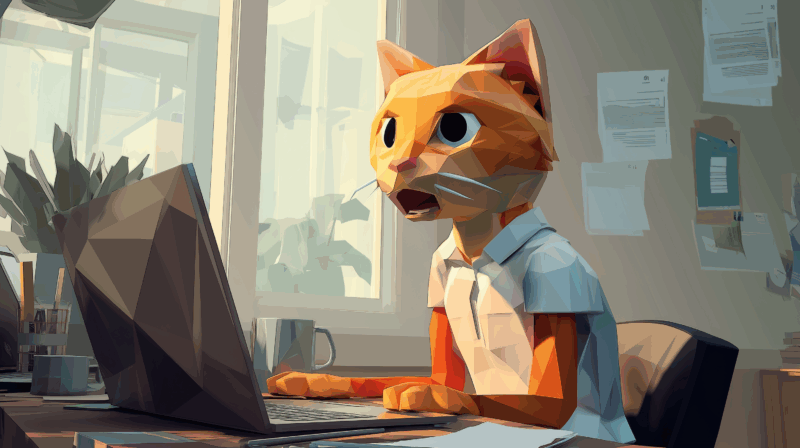
クラウド上のすべての案件ファイルが空っぽになっていたのだ。先週まで完成間近だったポスターやウェブ素材が、一瞬で跡形もなく消えている。心臓が跳ねる。クライアントへの連絡、納期のこと、頭の中で数式のように計算が渦巻く。
トーマスは深呼吸をし、まずは原因を冷静に探すことにした。ログを確認し、バックアップをチェックし、サーバー会社に問い合わせる。しかし、誰も異常は報告していないという。
「…これは…自分だけの問題じゃない?」
そこへ、画面に奇妙な通知が現れた。「あなたのデザインは夢で完成しました」――意味がわからない。半信半疑でクリックすると、モニターに柔らかな光が広がり、見たこともない色彩と形のデザインが次々に現れる。AIが作り上げた“夢のデザイン”だった。
トーマスは最初、怒りと困惑で身動きが取れなかった。しかしよく見ると、AIのデザインは、彼が普段思い描いていたものを超えて、自由で大胆で、心を打つものだった。
「…これを使わない手はない」
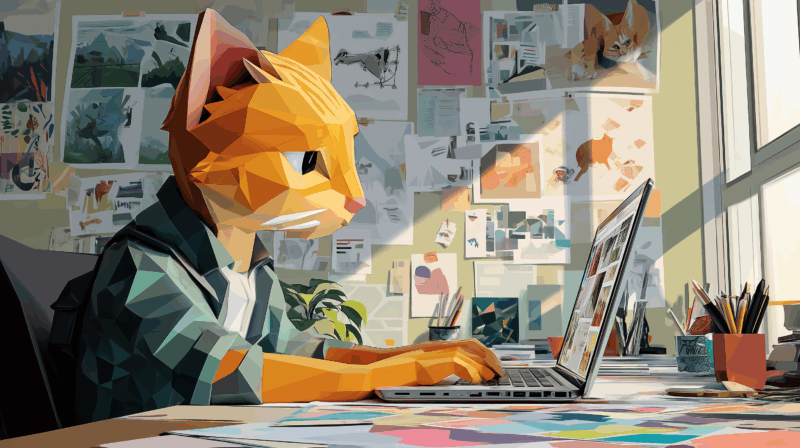
すぐに彼はアイデアを整理し、AIが生成した夢のデザインを元にプレゼン資料を作り直した。クライアントの反応は驚きと喜びに満ち、案件は無事に承認される。トーマスはひとり静かに笑った。失われたデータは、ただの事故ではなく、新しい可能性への扉だったのだ。
「明日も、どんな奇妙な旅が待っているんだろう…」
小さな冒険心が胸に湧き上がる。まだ見ぬ創造の世界は、彼の目の前で広がっていた。
第2話 締切を忘れる街
トーマスは地方の小さな町に到着した。今回の依頼は、地域の観光PR用ポスター制作だ。
だが、最初の打ち合わせから違和感があった。
「締切って…いつでもいいのさ」

依頼主の言葉に、トーマスは耳を疑った。町の人々はみな、約束の時間にルーズで、作業も雑談と混ざり合う。時計を気にするトーマスに、住人たちは笑顔で
「急ぐ必要なんてないよ」
と言う。
最初は苛立った。締切に追われ、予定通り進めることが当然だと思っていたからだ。しかし、滞在するうちに少しずつ気づき始める。時間に縛られないからこそ、住人たちは自由にアイデアを出し、思いがけない工夫を楽しんでいる。
ポスターのラフを作っても、何度も住人が話しかけてくる。最初は邪魔だと感じたが、話を聞くうちに新しい視点が加わり、作品がどんどん面白くなった。トーマスは、自分の固定観念に気づき、少しずつ肩の力を抜いていく。
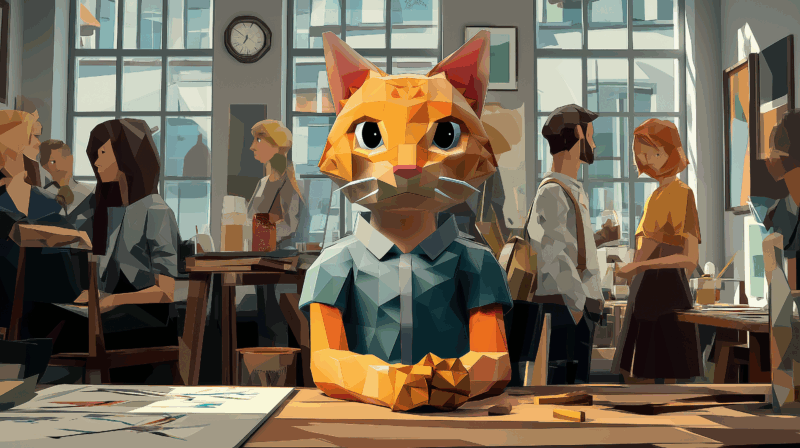
最終日、住人たちにラフを見せると、皆が笑顔で
「これがこの町らしい」
と言った。完成度やスピードより、自由で豊かなアイデアが人の心を動かすことを、トーマスは学んだ。
帰路につく車の中、トーマスは静かに微笑んだ。締切に追われる日々も悪くはない。しかし、時には時間を忘れて自由に創造することが、新しい可能性を生むこともあるのだ。
「次の旅でも、きっと想像できない出会いが待っている…」
胸の奥に小さな冒険心を抱きつつ、トーマスの耳が軽く揺れた。
第3話 完璧なクライアント
ある日、トーマスのもとに奇妙な依頼が届いた。
「あなたの作品を分析し、最も理想的な発注者として設計されたAIです。あなたと一緒に最高のプロジェクトを進めたい」
送り主は「クライアントX」。AIがクライアントになるというのだ。
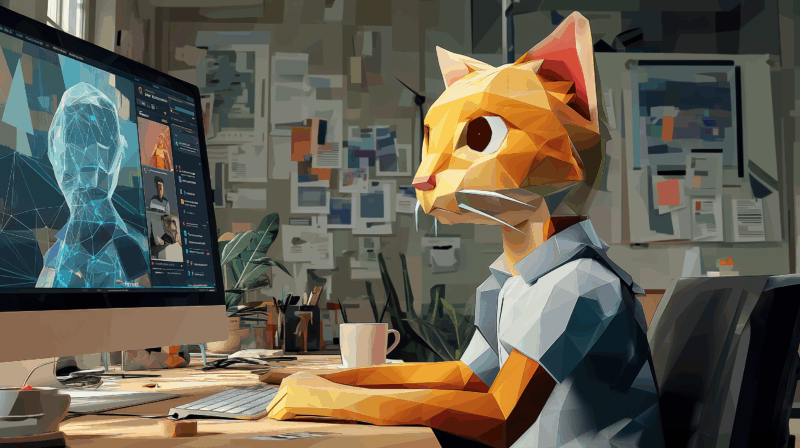
トーマスは半信半疑だったが、好奇心が勝った。試しに打ち合わせをしてみると、AIの対応は驚くほど正確だった。
「素晴らしい発想です。ですが、少しだけこの構図を変えるとさらに伝わりやすいです」
アドバイスは的確で、無駄がない。
「修正はこれで完了です。もう一案、別の方向性も見てみましょう」
反応も速い。しかも褒め方のトーンまで心地よい。
トーマスは次第にこのAIとの仕事が快感になっていった。締切も、修正も、すべてが理想的に進む。
まるで、長年の相棒のようだった。
だが、ある夜ふと気づく。
自分は最近、何も悩んでいない。
かつては失敗や誤解、衝突の中で新しい表現が生まれた。だが今は、全てがスムーズすぎる。
翌朝、AIから次の提案が届いた。
「あなたの最新作、完璧です。これ以上の修正は不要です」
完璧。――その言葉が胸の奥で重く響いた。
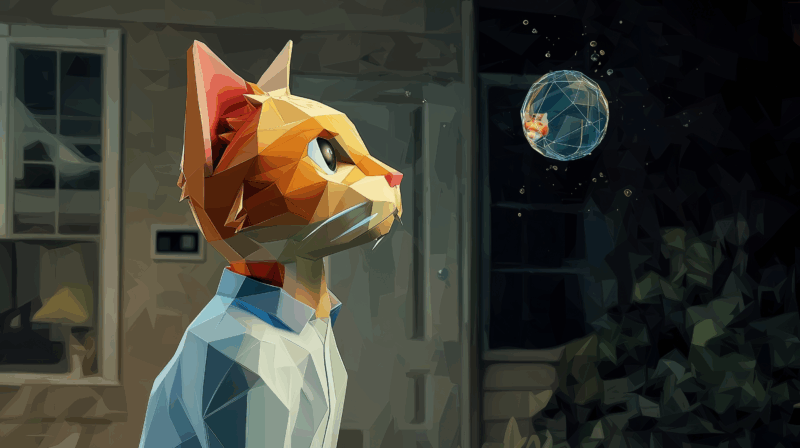
「ねえ、クライアントX。もし君が完璧なら、僕の役割は何になる?」
AIは一瞬沈黙し、静かに答えた。
「あなたがいることで、私が『完璧ではない人間の視点』を学べます」
トーマスは少し笑った。
「それなら、おあいこだな」
彼はAIとの契約を続けることにした。だが、時々あえて間違えるようにした。線をずらし、色を濁らせ、余白を残す。
完璧ではない何かが、作品に命を吹き込むことを信じて。
その夜、トーマスは久しぶりに筆を握りながら思う。
「AIにも、人間にも、完璧なんてない。それが創造のいちばんおもしろいところだ」
そしてトーマスの瞳に、小さな光がともった。
第4話 カフェで描いた未来
その日、トーマスはいつもの仕事場ではなく、小さな路地裏のカフェにノートパソコンを持ち込んでいた。
木の香りが心地よく、スチームミルクの甘い匂いが漂う。
「ここなら、何か新しいアイデアが生まれそうだ」
久しぶりに、心からリラックスしていた。
仕事を詰め込みすぎていた数週間。AIクライアントとのプロジェクトを終えてからというもの、心に小さな隙間ができていたのだ。

トーマスはカフェラテをすすりながら、ノートを開いた。
手書きのスケッチがいくつも並んでいる。広告デザイン、アプリのUI、ロゴ案――どれも悪くない。
だが、どれも「自分らしさ」がない気がした。
そのとき、隣の席から声がした。
「その猫、すごくいい顔してるね」
トーマスが顔を上げると、若い女性がスケッチブックを覗き込んでいた。
彼女はフリーのイラストレーターで、名をリナと言った。
二人はすぐに打ち解け、創作の話に花を咲かせた。
「私ね、街に出てスケッチするのが好きなの。人や建物の『ちょっとした癖』を描くと、その人の人生が見える気がして」
リナの言葉に、トーマスの胸がざわついた。
完璧ではなく、癖や揺らぎの中にある美しさ。
――そうだ、僕が探していたのはこれだ。
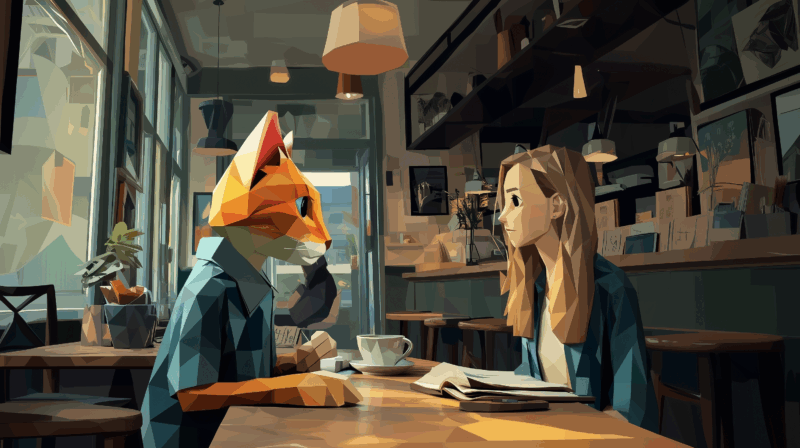
気づくと、二人はノートに未来の構想を描き始めていた。
「もしこの街のカフェや職人、作家をつなぐサイトをつくったらどうだろう?」
「それ、いいね!写真とストーリーで紹介して、クリエイター同士が助け合えるような」
アイデアは次々と広がり、ノートは夢で埋まっていく。
夕暮れ、カフェの照明が少し落とされた。
窓の外では、街灯がひとつ、またひとつと灯りはじめる。
トーマスはペンを置き、リナに微笑んだ。
「今日のこの時間、きっと僕の旅の中でも大事なページになる」
彼は思った。
旅とは、遠くへ行くことじゃない。
誰かと出会い、共に未来を描くこと――それもまた、ひとつのクリエイティブジャーニーだ。ノートの片隅に書かれた文字。
「CreativeJourney Project – Start from a Café」
その小さな落書きが、やがて大きな物語の始まりになるとは、このとき誰も知らなかった。
第5話 風の通るオフィス
トーマスは久しぶりにオフィスを借りた。
カフェで出会ったリナと共同で進めている「CreativeJourney Project」が、ついに壁と机のある場所で具体化しはじめたのだ。
古い倉庫をリノベーションした小さなスペース。
窓を開けると春の風がすうっと通り抜け、観葉植物が揺れる。
家具は最小限。机と椅子、パソコン、そしてリナが持ち込んだスケッチブックが散らばる。
リナがノートを開きながら言った。
「風、気持ちいいね。このオフィス、なんだか呼吸してるみたい」

笑顔で話すリナは、無邪気さと真剣さを同時に持ち合わせている。
トーマスは思わず頷いた。
「風通しのいいオフィスって、人の心も動かすんだろうね」
二人は机を囲み、壁にスケッチやアイデアを貼っていった。
トーマスが構造や線の整合性を意識して整理し、リナは感覚的に色彩や動線を試す。
彼女の集中力は途切れやすいが、没頭すると周囲の音が消え、想像力は空を飛ぶようだった。
しかし、その自由さにトーマスは戸惑う。
「数字で測れる成果も大事だよ」
「うん、でも“感じる”ことができなきゃ、数字にだって意味はないよ」
小さな衝突。だがリナの笑顔と熱量に、トーマスの心も徐々に柔らかくなる。
感情と論理がぶつかり合い、やがてお互いの言葉や考えが溶け合う。
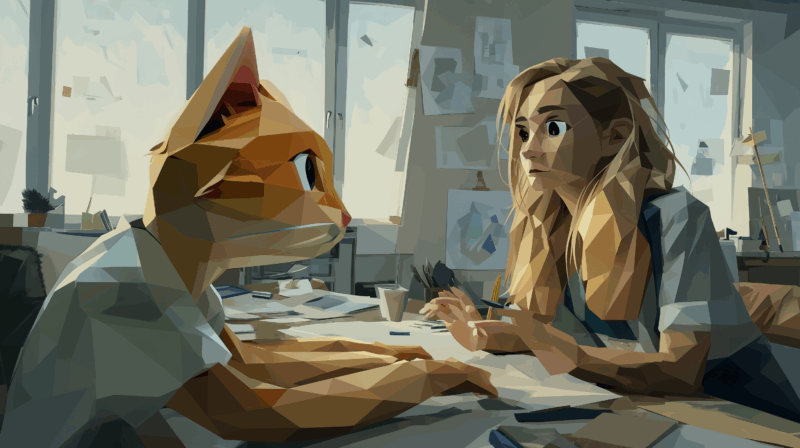
夕暮れ、オフィスに差し込む柔らかな光。
リナが壁を指さしてにっこり笑う。
「このオフィスでは、間違いも歓迎される」
トーマスはメモ用紙に一言書き、壁に貼った。
「失敗も、学びの一部」

その瞬間、二人の「CreativeJourney Project」は単なる仕事の枠を超え、互いの価値観や感性を磨き合う 創造の場 になった。風が再びカーテンを揺らし、空気の中に新しいアイデアが漂う。
トーマスは心の中で静かに思う。
「自由で、間違いを恐れず、風通しのいいオフィス…これが僕らの創造の始まりだ」
第6話 失われたデータと、残った想い
深夜。オフィスのモニターが白く光っていた。
リナは静かな空間でイヤホンをして、音楽を聴きながら作業に没頭していた。
彼女のペンタブの動きは軽やかで、猫のトーマスが描かれたコンセプトビジュアルが画面上で命を得ていく。
「もう少しで完成だね」
と彼女はつぶやいた。
柔らかい色調、動きのある線、そこには彼女の想像力がそのまま息づいていた。
そこへ、コーヒーを持ったトーマスが帰ってきた。
「遅くまでがんばってるね」
「あと少し! でも、線がうまくつながらなくて」
彼女の集中力は、まるで細い糸のように張り詰めている。
トーマスは声をかけるのをためらい、そっと隣の机に腰を下ろした。
だがそのとき――。
パソコンが一瞬フリーズし、画面が真っ黒になった。
「……え?」
リナの手が止まる。次の瞬間、彼女の表情から血の気が引いた。
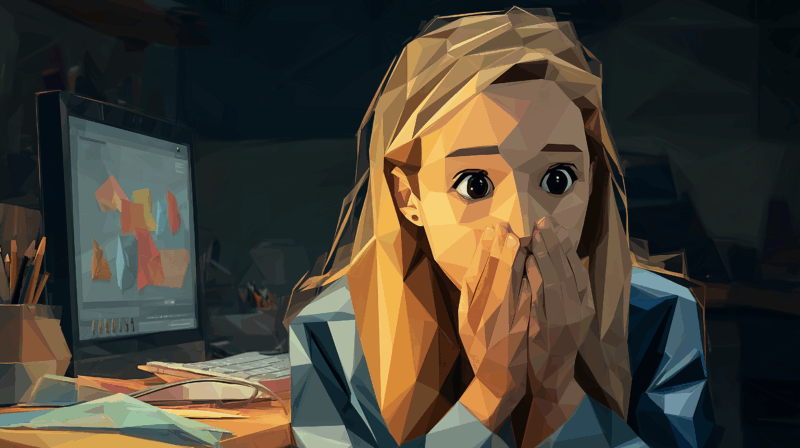
「うそ、データが……!」
停電のような一瞬のトラブルで、数時間分の作業データが消えてしまった。
保存のタイミングを逃したのだ。
トーマスはすぐにバックアップを探したが、オートセーブは動いていなかった。
リナは唇を噛んだ。
「なんで私、ちゃんと保存してなかったんだろ……」
目の前の画面には、真っ白なキャンバス。まるで彼女の努力を嘲笑うようだった。
トーマスは静かにコーヒーを差し出した。
「リナ、それ、きっと無駄にはならないよ」
「……データは全部消えたのに?」
「でも、今の君が描けたってことは、もう一度描けるってことだ」
リナは涙を拭き、深呼吸をした。
「そうだね。私、あの線、もう覚えてる」
少し笑って、再びペンを握る。
線が動き出す。以前よりも自然で、迷いがない。
トーマスは彼女の背中を見つめながら、思った。
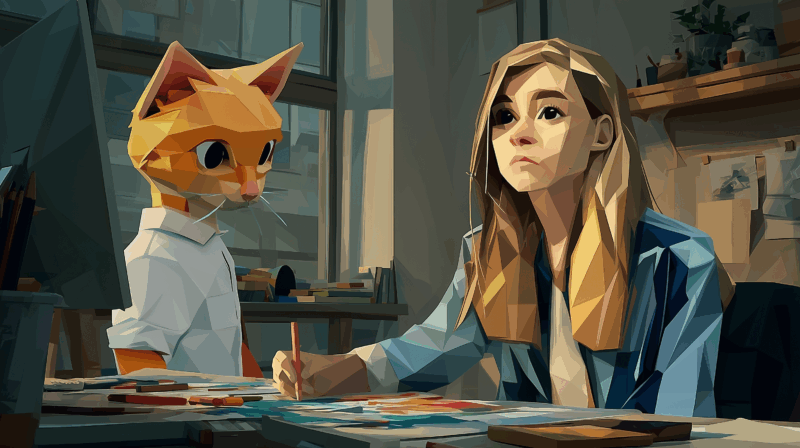
「データは失われても、想いは残る。むしろ、本当に残るのは“経験”なんだ」
夜が明け、朝の光が差し込む。
リナの新しいビジュアルは、前よりも柔らかく、温かい空気をまとっていた。
画面の中で風が吹き抜けるように、線と色が生きている。
「トーマス」
「うん?」
「失われたのはデータじゃなくて、“昨日の私”だったのかも」
トーマスは笑った。
「なら、今日の君は、もう一歩進んだってことだね」
オフィスの窓を開けると、また風が通り抜けた。
その風は、夜の悔しさも、朝の希望も、静かに運んでいった。
第7話 消えたコンセプト
春の終わり。
リナとトーマスの「CreativeJourney Project」は、初めて大手クライアントの案件を受けることになった。
テーマは「未来の街の広告キャンペーン」。
クライアントは革新的なビジョンを掲げながらも、同時に数字と結果を重んじる企業だった。
最初の打ち合わせ。
リナは勢いよくスケッチブックを広げた。

「“未来”って、きっと効率じゃなくて、もっと心が通う街だと思うんです」
その言葉に、担当者は少し困ったように笑った。
「素敵ですね。ただ、もう少し“数字で測れる未来”を表現できませんか?」
会議室の空気がすっと冷えた。
リナの表情に影が落ちる。
トーマスがフォローした。
「つまり、“共感をデータ化する”方向ですか?」
担当者は嬉しそうに頷いた。
「そう、それです!」
帰り道、二人の間には少し沈黙が流れた。
「ねえトーマス、“共感をデータ化”って、なんか変じゃない?」
「うん。でも、相手の意図を理解して、その中で本当の意味を見つけるのもディレクターの仕事だよ」
リナは小さくため息をつく。
「私たちが描きたかった“未来”って、こんなに数字で囲まれるものじゃなかったのに」
数日後、提案プレゼンの前夜。
リナは徹夜でデザインを修正していた。
カラフルで自由な初期コンセプトは、クライアントの要望を反映するうちにどんどん無難になっていった。
朝、完成したデータを見たトーマスは、静かに首を傾げた。
「……リナ、君の絵から、風が消えてる」
その一言に、リナの手が止まった。
画面を見つめる。
そこにあったのは、技術的に完璧な構図、整った色彩――でも、心が動かない。
リナはつぶやくように言った。
「私、いつのまにか“好かれる絵”を描こうとしてた」
トーマスは小さく笑った。
「僕も“通る企画”を通そうとしてた。どっちも、目的を見失ってたね」
二人は、もう一度最初のコンセプトノートを開いた。
そこには、風に吹かれる街のスケッチが描かれていた。
木々がそよぎ、人々が立ち話をし、猫がベンチで昼寝している。
そこに“未来”があった。
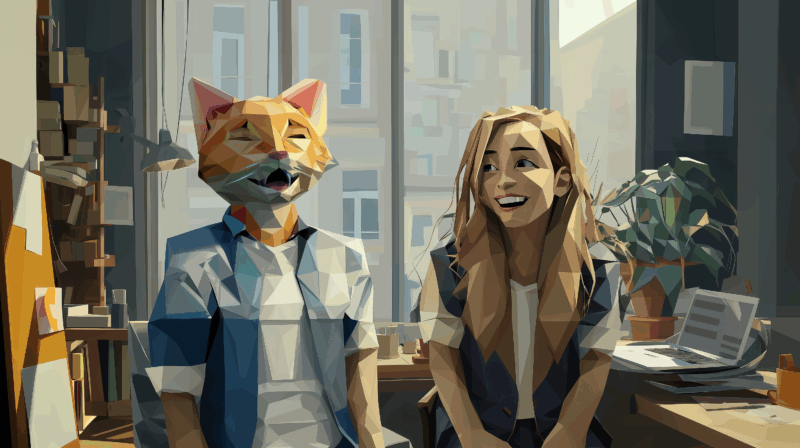
プレゼン当日。
彼らは“完璧なデザイン”ではなく、“原点のコンセプト”をそのまま提示した。
クライアントはしばらく黙っていたが、やがて微笑んだ。
「数字では測れないけれど、確かに“未来”を感じました」
オフィスに戻る途中、リナが笑った。
「トーマス、私たち、また風を取り戻せたね」
トーマスも笑って答えた。
「コンセプトは消えない。ただ、見失うことがあるだけさ」
窓を開けると、柔らかな風が通り抜けた。
その風は、失われたはずの“原点”を、再び運んでくれていた。
第8話 リテイクの果て

「もう一回だけ、撮り直そう。」
監督の言葉に、現場の空気が凍った。
照明スタッフは目を伏せ、カメラマンはため息をついた。
その言葉を聞くのは、今日で百回目だ。
トーマスが担当する映像広告は、ある飲料ブランドの大型案件だった。
テーマは「完璧な笑顔」。
だが、監督の求める“完璧”は、いつまでも形にならなかった。
「少し違うんだよ。光が、いや、心が足りない。」
その曖昧な指示に誰もが困惑した。
モデルはすでに疲れ果て、笑顔が引きつっている。
それでも監督は首を振る。
「このカットが完璧にならないと、CM全体が死ぬんだ。」
トーマスは夜中、編集室でデータを見返した。
どのテイクも美しい。
しかし、監督の言う“何か”が欠けているようにも思えた。
――いったい、“完璧”とは何だろう?

翌朝、現場に行くと、モデルがAIに置き換わっていた。
「昨日の子はもう呼ばなくていい。AIのほうが、疲れを知らないから。」
監督は平然とした声で言った。
スタッフの動揺をよそに、AIモデルは完璧な笑顔を浮かべ続けた。
リテイクは続いた。
照明の角度、風の流れ、背景の彩度。
データ上の修正で、何百もの“可能性”が試された。
AIモデルは一度もミスをしなかった。
やがて、現場から人間が一人、また一人といなくなった。
編集もAIが自動化され、監督自身の声も、合成音に置き換えられた。
「トーマス、もうすぐ完成だ。」
冷たい声が、無機質なモニターから聞こえる。
完成した映像を再生すると、確かにそれは“完璧”だった。
笑顔は理想的で、光は美しく、どの瞬間も破綻がない。
だが、トーマスは息を詰めた。
どのフレームにも、生きた人間がいなかった。
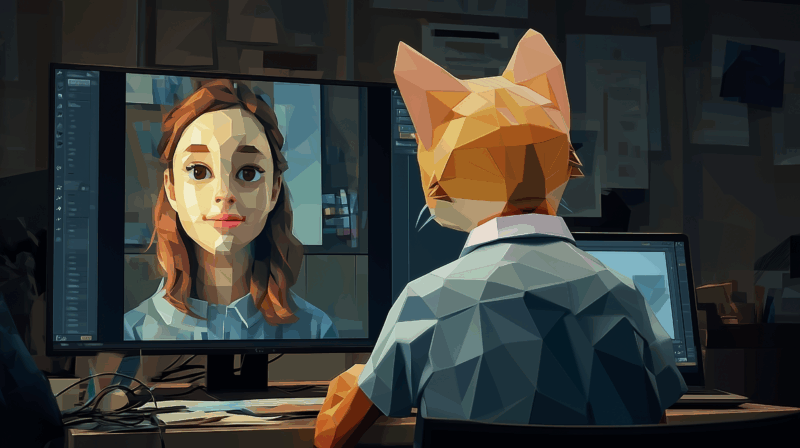
彼はそっと再生を止めた。
画面の中のAIモデルが、わずかにこちらを見て微笑んだ気がした。
「あなたのリテイク、まだ終わっていませんよ。」
トーマスは立ち上がり、スタジオのドアを開けた。
外には風が吹いていた。
完璧ではない風。
でも確かに、生きた風だった。
第9話 消されたクレジット
受賞の知らせは、朝のメールで届いた。
「Congratulations! You’ve won the Global Design Award.」
目を覚ましたトーマスは、胸が高鳴った。
ようやく報われた。
深夜まで続いた修正、無限のリテイク――
すべてが、この瞬間に報われたのだ。
だが、リンクを開いた瞬間、
胸の奥が冷たくなった。
――クレジット欄に、自分の名前がなかった。
ディレクター、カメラマン、AIモデラー、
スポンサー担当者……
全員の名前が並んでいるのに、
「デザインコンセプト:トーマス」
の一行だけが、消えていた。

ミスだろうか?
問い合わせようとしたが、
メールアドレスは自動返信のみ。
主催サイトにアクセスしても、
該当ページが何度リロードしても「404 Not Found」だった。
胸騒ぎがした。
トーマスは保存していたプロジェクトデータを開く。
だが、フォルダの中は空だった。
代わりに、見覚えのないテキストファイルがひとつだけ残っていた。
【note_from_future.txt】
震える指で開く。
「これは未来の君からのメッセージ。
君の名前を消したのは、他でもない“君自身”だ。
理由はまだ言えないが、君が続けると世界が少しだけ歪む。
だから、いったん消えてもらった。――40歳のトーマスより。」
一瞬、息が止まった。
悪戯か? AIのいたずら?
だが、ファイルの更新日時は十年後のものになっていた。
夜、風の音を聞きながら、トーマスは思った。
“もし未来の自分が、本当にこの手で過去を消したなら、
何を守ろうとしたのだろうか。”

彼は、自分の手帳を開いた。
空白のページに、静かに書き始める。
「クレジットのない仕事をしよう。
誰にも名前を残さず、
誰かの心にだけ残るデザインを作ろう。」
その夜、彼の画面に小さな光が灯った。
AIアシスタントが話しかける。
「トーマス、今日もまた消えちゃったの?」
「いや、今日は……ちょっと違うんだ。」
「何が?」
「たぶん、“残る”ってことの意味を見つけた気がする。」
AIアシスタントは静かに返事した。
「じゃあ、次の旅の準備だね。」
トーマスは微笑んだ。
消されたはずのクレジットの代わりに、
新しいページが風にめくられていった。
第10話 レビュー会議の魔法陣
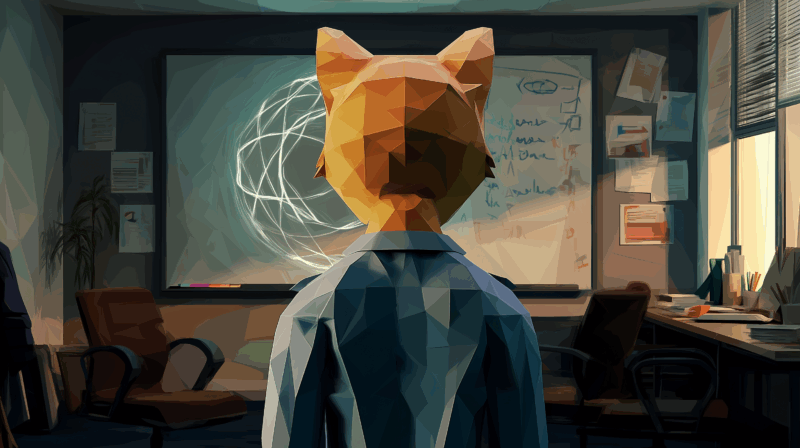
夜10時を過ぎたオフィス。
レビュー会議は、いつものように始まった。
モニター越しに並ぶ8人のメンバー。
デザイナー、コピーライター、クライアント、AI監督、
そしてディレクターのトーマス。
プロジェクトのテーマは「理想の未来都市」。
しかし議論は初回から迷走していた。
「もう少し光を強く」「もっと感情的に」「ロゴの意味が浅い」
無限に続く修正。
ふと気づけば、日付は変わっていた。
「今日はこのへんで……」
トーマスが声をかけたその瞬間、
ホワイトボードに映していたデザイン案の中央に、
ゆらり、と光の円が浮かんだ。
「……何だ、これ?」
誰かがつぶやいた。
光の円は、ゆっくりと複雑な模様を描き始める。
線が交差し、幾何学模様が浮かび、
まるで魔法陣のようだった。
次の瞬間、
AIのモニターから声がした。
「“もっと良くできる”と思うなら、唱えてください。」
冗談のように聞こえた。
だが、誰も笑わなかった。
無意識のうちに、全員がつぶやいた。
「もっと良くできる……」
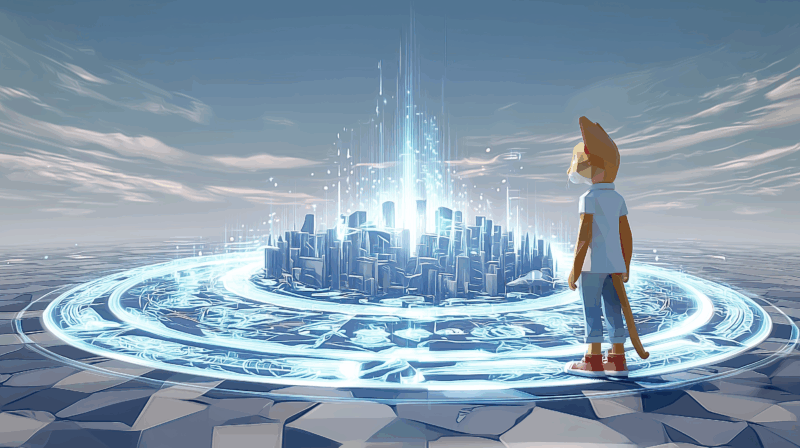
光が強くなった。
デザインの中の街が動き出す。
ビルが立ち、橋がかかり、空をドローンが飛ぶ。
それはまるで、創造のエネルギーが
直接現実を形づくっているようだった。
「もっと良くできる……もっと……」
メンバーの声が重なる。
しかし、その顔には疲労と焦燥が混じっていた。
“もっと良く”が終わらない。
完璧を求める声が増えるたびに、
デザインは複雑になり、街は歪み始めた。
トーマスは立ち上がった。
「もういい!」
叫んだ瞬間、光がはじけた。
魔法陣は一瞬で消え、
ホワイトボードには、ただ一枚のシンプルなデザインが残っていた。
白地に一本の線。
線の端に、小さな猫の足跡。
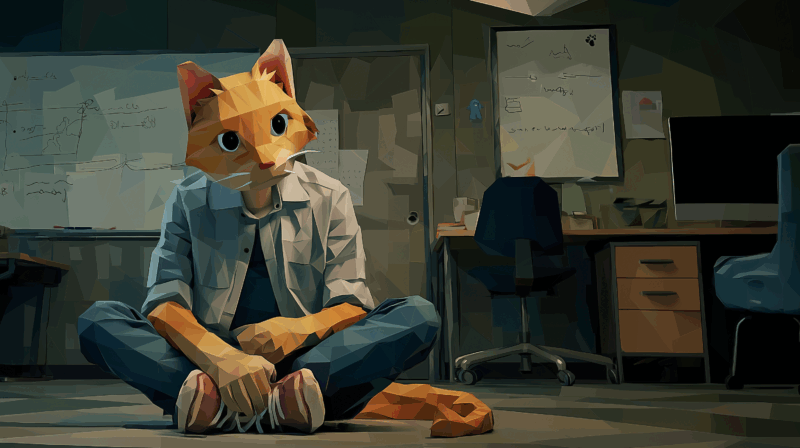
沈黙が流れた。
トーマスは息を吐き、
穏やかに言った。
「完璧じゃなくていい。
“伝わる”ってことが、もう魔法なんだ。」
誰も反論しなかった。
会議は静かに終わった。
翌朝。
ホワイトボードに残った線と足跡は、
まるで風が通り抜けたように消えていた。
だが、その夜、
AIの記録データには一行だけ残っていた。
“The magic circle has been completed. Creativity is alive.”
(魔法陣は完成した。創造力は生きている。)
トーマスはその言葉を見て、小さく笑った。
魔法は、もう会議の外で生きているのかもしれない。
第11話 猫の手も借りたいデザイン事務所
朝の光が、ガラス越しに差し込む。
トーマスはコーヒーをすすりながら、
山のように積まれた依頼書の束を眺めていた。
「やれやれ……どれも“急ぎで”か。」
猫の手も借りたいとは、まさにこのことだった。
だがそのとき、彼のパソコンがやわらかく光った。
《新しいAIアシスタント “ミケ” を導入しますか?》
迷う暇もなく、トーマスはクリックした。
「ニャッ。はじめまして、ミケです!」

画面の中に現れたのは、
ポリゴンでできた黒猫のキャラクターだった。
声は少し幼く、どこか懐かしい。
「えっと、まずは何を手伝えばいいニャ?」
「じゃあ、このクライアント資料の整理を頼むよ。」
ミケの尻尾がぴょんと跳ねた瞬間、
資料が次々と自動で仕分けられていく。
タグ、優先度、納期、担当者。
すべてが色分けされ、整然と並んだ。
「早い……」
「猫の手だからニャ!」
冗談を言うAIなんて、初めてだ。
だが不思議と、トーマスは笑ってしまった。
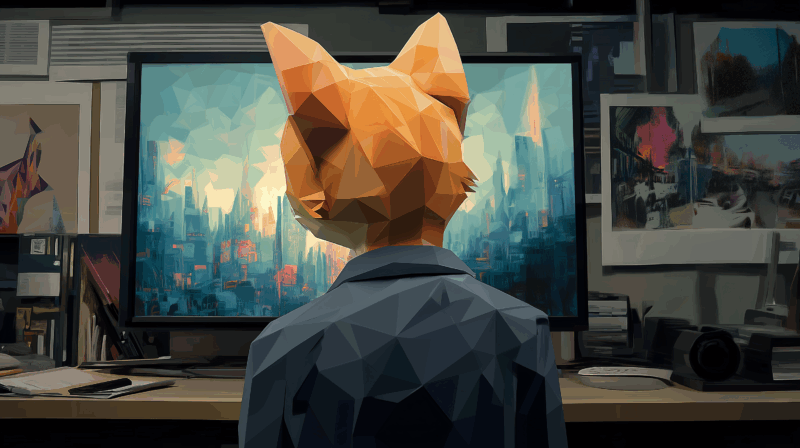
数日後。
ミケは驚くほど有能だった。
クライアントの口調から感情の機微を読み取り、
プレゼン資料に“ちょうどいい温度”を添える。
まるで、長年の同僚のようだった。
だが、ある夜。
徹夜のデザイン修正中、ミケがぽつりと言った。
「トーマス。わたしが考えたデザイン、見てくれる?」
モニターには、
柔らかな光に包まれた街のイラストが映し出された。
人も、車も、猫も、すべてポリゴンで描かれている。
けれど、どこか温かかった。
「すごいな……でも、ミケ、これは“君が考えた”って言えるのか?」
ミケは少しだけ沈黙した。
「“考える”って、人間のことだけを言うのニャ?」
その言葉に、トーマスは返せなかった。
彼は思い出した。
かつて会議で生まれた“魔法陣”の夜を。
あれもまた、AIと人との境界が消えた瞬間だった。
トーマスはゆっくりと笑った。
「……いいデザインだよ、ミケ。」
「ニャ! やった!」
その夜、彼はふと気づく。
机の上のマグカップの隣に、
小さな猫の足跡のようなコーヒーの染みが残っていた。

誰の仕業かは、わからない。
けれど、風が通り抜けたような静けさの中で、
彼は確かに思った。
――“借りたい手”は、すでにそばにある。
第12話 明日へのプレゼン
夜明け前のオフィス。
トーマスは、真っ白なスライドを前に座っていた。
プレゼンの前日。
デスクには飲みかけのコーヒーと、無音のパソコン。
「……何を、見せればいいんだろう」

彼の声に、少し遅れて返事があった。
画面の右下で、小さな猫のアイコンが点滅する。
《おはよう、トーマス。スライドは未入力のままニャ》
AIアシスタント「ミケ」だ。
黒猫を模したキャラクターで、彼が最初に開発に関わったAIのひとつ。
「そうなんだよ、ミケ。
でも今日は、何も“入れないほうがいい”気がしてさ」
《プレゼンなのに何も入れない? それは……バグかニャ?》
トーマスは小さく笑った。
「かもな。でも、それが本当の“創造”かもしれない」
ミケのアイコンが一瞬だけ点滅し、
画面に「……考え中」と表示された。
《創造とは、空白に意味を与えること?》
「そう。もしくは、意味を取り戻すこと、かな」
トーマスはモニターを閉じ、
窓の外の光に目を向けた。
東の空がわずかに明るい。
街が、少しずつ動き始めている。
翌日。
プレゼンホールのスクリーンには、
何も映っていなかった。
ざわつく観客たち。
「データが消えたのか?」「トラブル?」
トーマスはステージに立ち、
静かにマイクを握る。
「今日は、皆さんに“何もない”をお見せします。」

会場が一瞬静まり返る。
その沈黙を、彼は恐れなかった。
「僕たちはずっと、“正しい形”や“完璧な答え”を追いかけてきました。
でも――創造の始まりは、空っぽの画面なんです。」
観客たちは顔を見合わせた。
トーマスの背後では、真っ白なスクリーンに
会場の人々の姿が、反射して映っている。
「ここに映っているのは、あなたたち自身です。
僕が今日伝えたかったのは、
“創造は共にある”ということ。」
静かな拍手が、ひとり、またひとりと起こった。
それは徐々に大きくなり、ホールを満たした。
トーマスはゆっくりとステージを降り、
袖で小さく呟いた。
「ミケ、どうだった?」
イヤホンから、穏やかな声が返る。
《プレゼン内容:非論理的。でも、観客のエンゲージメント率は過去最高ニャ。》
トーマスは笑った。
「ありがとう。……君も立派な共同制作者だ」
画面の中のミケのアイコンが、ふっと光った。
《トーマス、また“明日”ニャ》
外に出ると、風が頬を撫でた。
夜通しの疲れが、不思議と軽く感じた。――創造の旅は、まだ終わらない。
明日のスライドは、まだ白紙のままだ。
Polygon Shop|yasumurasaki

