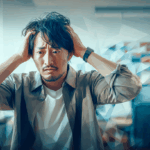子どもが足し算・引き算の算数ドリルをするようになりました。
ちょっと前までバブバブ言っていたのに、成長は早いなぁと感じます。『スラムダンク』という有名な漫画に、「日々成長する姿を見るのは道楽だ」と言っていた安西先生の言葉がわかります。それと同時に自分が子どものころは、親から似たような目で見られていたのだろうか?と思います。
さて算数ドリルについて、穴埋め問題のような機械的な処理をする問題が多いです。ですがそのあとくるのは文章問題です。例えば以下のような感じです。
「ヨットと うきわが あわせて 7つに なるように ▲と ★を せんで むすびましょう。」
問題文の下には左にヨットの絵があり、右に浮き輪の絵があります。右と左を足すと7にな
る絵が4組、ランダムに並んでいます。ヨット側の▲と浮き輪側の★を合計7になる組み合わせで線を結びます。ほかの問題では、
「ぜんぶで 7この かいが あります。なんこと なんこに わけられますか。□に数字を かきましょう。」
問題文の下には例えば「6こと □こ」のように、片方の数字が書いてあり、もう一方は空欄になっている状態です。この空欄に数字を入れて、合計7になるようにします。
わが子はありがたいことに、穴埋め問題はできるので足し算・引き算自体はできるようです。しかしこの文章問題がなかなか強敵なようです。どうしてわからないのかよく聞いてみました。すると、そもそも何をどうしたらいいのかよくわからないらしいのです。
最初は意味がわかりませんでした。しかし問題をいくつかやっていくと、どうやら文章の意味がわからないらしいのです。つまり算数ドリルではあるものの、文章問題になると途端に文章読解という国語の問題があらわれるということです。
算数は高学年になるほど文章問題が増えていきます。つまり算数といえども、国語の読解力がないと少しずつ勉強についていけなくなるのではとハッとしました。
「英語習得は大事だけど国語の学習はもっと大事なんじゃないかと思うという話」でも書きましたが、英語についても同じように国語の勉強・習得は大事だと思います。そしてこれは算数にも当てはまるのでしょう。
だから速攻で読解力のドリルについて検索しました。そうしたら『国語読解力「奇跡のドリル」小学校1・2年』が良さそうでした。説明には「灘校を東大合格者数日本一に導いた伝説の教師とその授業の全貌を書いた単行本『奇跡の教室』の著者・伊藤氏貴 明治大学教授による小学校1・2年生向け国語ドリル」と書いてあります。即ポチでした。
読解力をはじめ国語の重要性は「AIが進化するほど頭の中のイメージを言語化する国語や語彙力が重要になるのではないかと思う話」でも以前書きました。国語は勉強や試験に限らず、その後の仕事や今すごいスピードで進化しているAIでも大事になります。
国語を中心に子どもの学習計画を練ろうかと思っているくらいです。とはいえ子どもにも好き嫌いや得手不得手があるので、そこは見極めながら楽しく一緒に学んでいこうと思います。