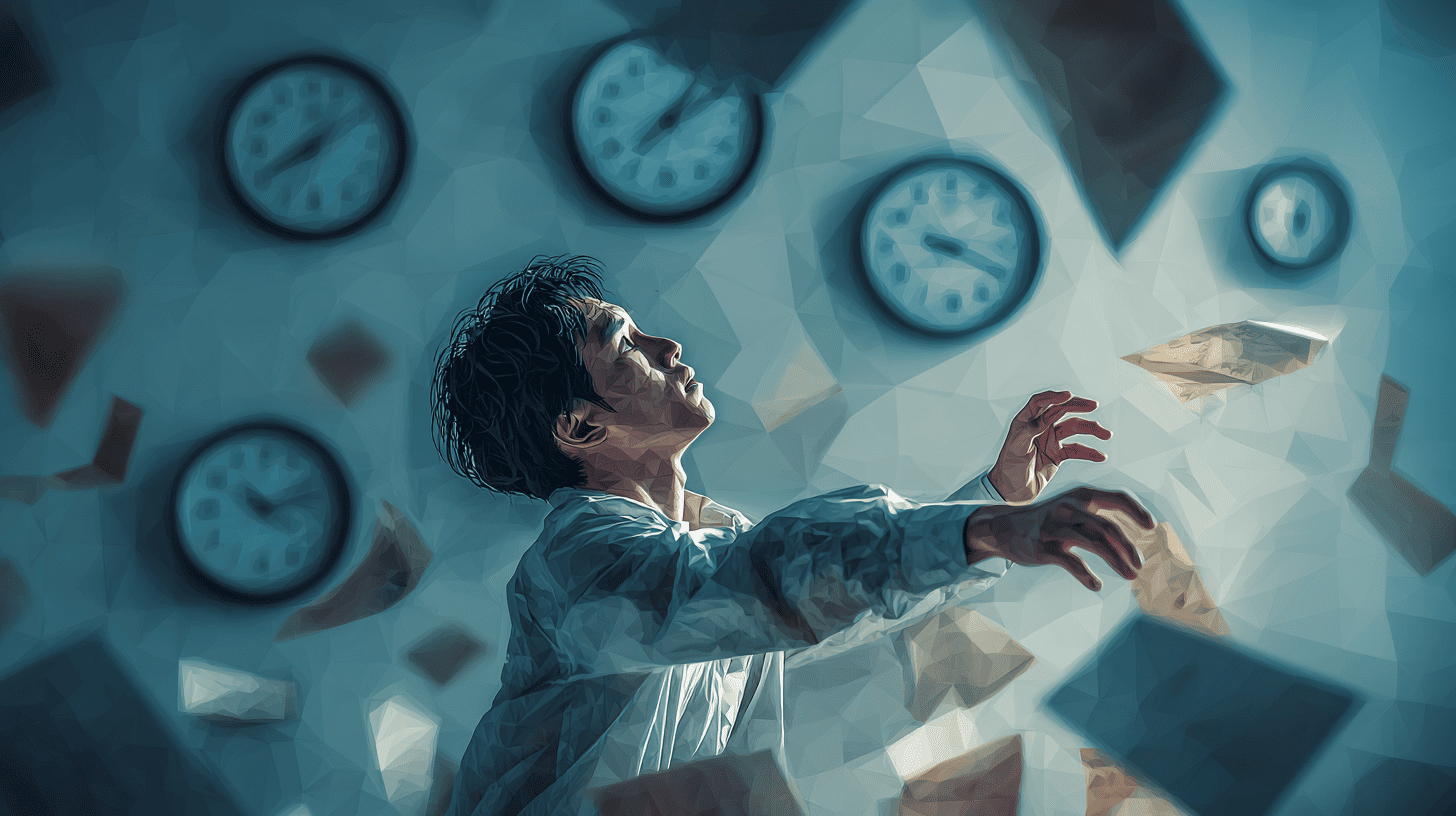これは制作に限らない話ですが、どんな仕事も納期は必ず守らなければなりません。契約によっていつまでに納品するかが取り決められている以上、それは絶対条件です。
制作の現場にいると、デザインにどうしても納得がいかないときや、コーディングやプログラミングの不具合がなかなか解消できず徹夜仕事になることなど、さまざまなトラブルに直面します。
しかしその中で最も恐ろしいのは、納品が遅れそうになる事態です。
制作の現場ではスケジュール調整は日常茶飯事です。
例えば私がパナソニックの仕事を担当していたときは、関係者の数が非常に多く、さまざまな立場から多様な意見が出ました。全員が同じ方向を向いていれば順調に進みますが、役割や立場の違いから意見が衝突することも珍しくありません。意見がぶつかるたびに、間に入ってヒアリングをし、落とし所を探していく必要がありました。これに時間がかかるのです。
さらに「鶴のひと声」、つまり肩書きのある上位者のひと言で、それまで積み上げてきた制作物がひっくり返され、ゼロからやり直しになることさえありました。
また、ウェディングの案件ではB to Cの仕事でしたが、お客様の意見が二転三転するのは当たり前でした。結婚式という人生の一大イベントだからこそ、依頼する側も悩み抜いて決断するのです。その結果、スケジュールは度々揺さぶられました。
さらに私たちは下請けの立場だったため、会場となるホテルやレストランの意向に逆らうことができず、現場の意見を飲まざるを得ませんでした。
一方で金融業界の案件ではB to Bでしたが、こちらもまた難しいものでした。金融業界特有の厳格さに加え、こちら側の立場が弱かったり、営業が強く意見を言えなかったりすることもありました。その結果、クライアントの無理難題に応えるしかないという状況が頻繁に起こりました。
こうした経験を通して実感したのは、クライアント側からすると「たった1日遅れただけ」と思われることが多いということです。しかし、実際にはまったく違います。
制作の現場は、営業やプロデューサーからディレクターへ、そこからデザイナー、カメラマン、レタッチャー、動画編集者、アニメーター、イラストレーター、コーダー、プログラマー、校正・校閲、製版、印刷所といった、多くの専門職が連携して成り立っています。それぞれが予定を合わせて動いているため、1日の遅れが全体に波及すると、都合がつかなくなる部分が必ず出てきます。
その結果、クライアントと営業の間で「1日遅れ」と認識されていたものが、制作全体の工程に落とし込むと「1週間遅れる」ことになったりするのです。
しかも納期そのものをずらすことはできません。だからこそ現場では、関係者全員に無理をお願いし、なんとかスケジュールを合わせてもらうしかありません。そのしわ寄せは制作側の時間や体力、さらには健康にまで及びます。徹夜や休日返上は珍しくなく、さらに1つの案件が遅れると、他の案件まで後ろ倒しになり、雪だるま式に遅延が膨らんでいきます。
スケジュールが変動する原因は数え切れないほど存在します。だからこそ大事なのは、最初にスケジュールを立てる段階で、関係各位に根回しをしておくことです。無理な部分やリスクがあれば、その時点で意見を吸い上げて調整することが欠かせません。
また、制作が始まってからも常に先回りして状況を確認し、日程がずれないように関係者にプレッシャーをかけていく必要があります。少々窮屈に感じられるかもしれませんが、それが結果として全体のスムーズな進行につながります。
結局のところ、納期を守るというのは信頼そのものです。
クライアントにとって納品が遅れることは、制作物のクオリティ以上に重大な問題となる場合もあります。だからこそ制作の現場では、1日の遅れを軽く考えてはいけません。1日が1週間になり、ひいては全員の負担と信頼の低下につながるのです。
制作スケジュールを守るというのは単なる日程管理ではなく、関わる全員の責任を背負った行為なのだと強く感じています。