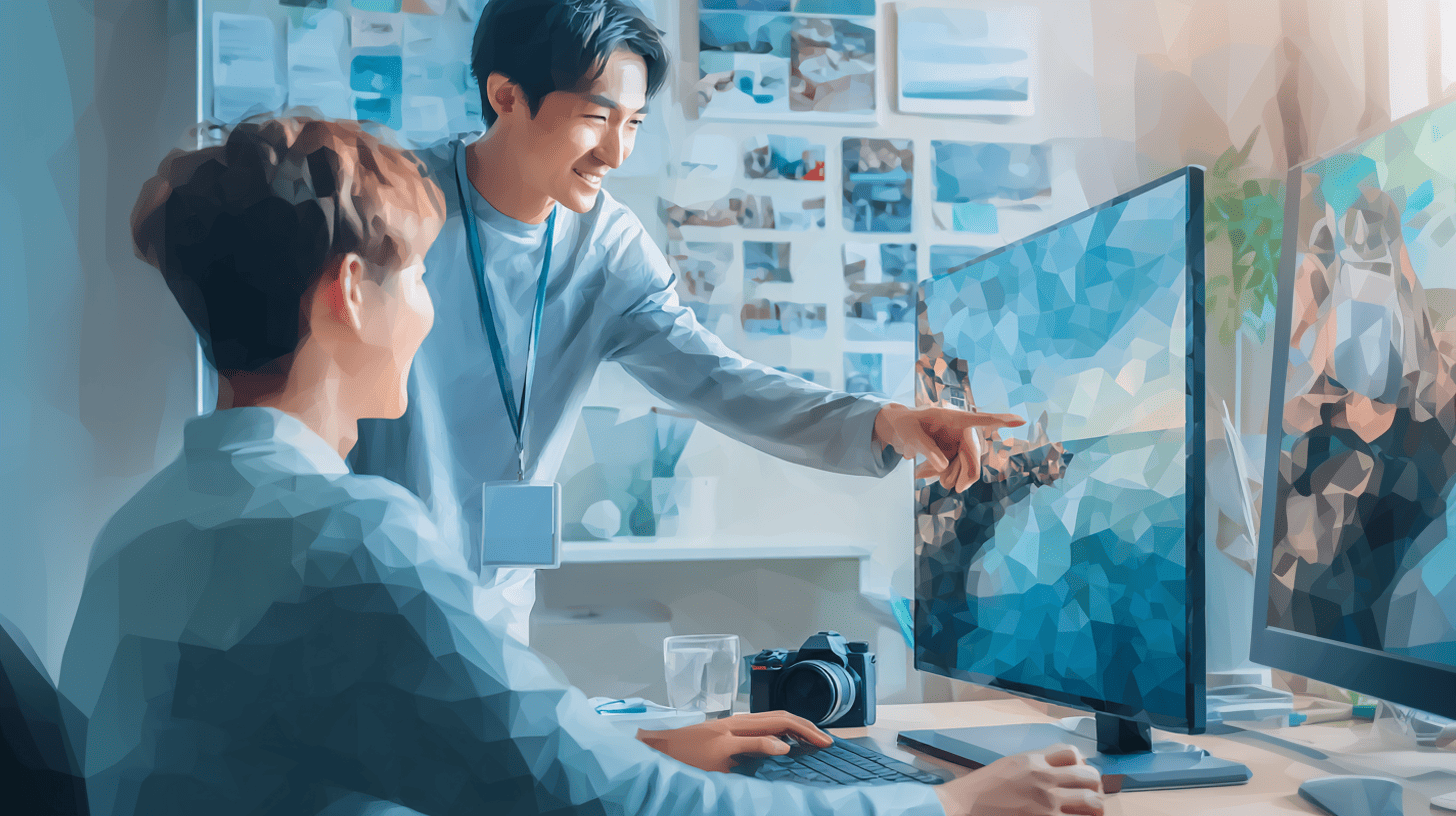パナソニックの子会社で制作ディレクターをしていたときのことです。
振り返ると、約6年間で担当した商品カテゴリーは10個ほどありました。新商品は年に2回発売され、そのたびに撮影が行われます。撮影は大きく分けて、商品のディテールを正確に伝える商品撮影と、モデルやロケーションを使ったイメージ撮影の2種類です。
単純に計算すると、3カテゴリー×年2回×6年間×2種類で、72回ほど撮影ディレクションをしてきたことになります。数字にしてみると、わりと多くの撮影現場を経験してきたのだと実感します。
撮影スタジオは毎回同じ場所を使うことが多く、多少のイレギュラーがあっても柔軟に対応してくれる安心感がありました。中には私より長くその商品カテゴリーに携わっているカメラマンもいて、こちらが求める前に提案を出してくれることもありました。
ただ、すべてを鵜呑みにするわけにはいきません。制作ディレクターとして一度受け止め、検討し、取り入れるか軌道修正するか、ときには却下する判断を下す必要があります。その役割を通じて、どの画像が最適かを見極める目が鍛えられました。
タイトルにあるように、撮影では「商品の細部まで見せる画像」と「コントラストを強めて印象を際立たせる画像」をどう使い分けるかが重要になります。
パナソニックのような事業会社では、自社商品を広報、広告、販促などさまざまな場面で発信していきます。それぞれの用途に応じて、求められる画像の方向性は大きく異なります。
広報では、プレスリリースや先行発表会で商品が紹介されます。プレスリリースは事実をもれなく発表する場であり、先行発表会ではメディア関係者や関係者が実際に商品を見て触れることもあります。ここでは、商品の細部までしっかり見せる画像が欠かせません。ボタンの位置や質感、サイズ感などが明確に伝わらないと、正しい理解や評価につながらないからです。
一方、広告では印象を優先させるイメージ画像が主役です。細部を説明するのではなく、商品の強みを象徴的に見せるため、光と影を強調し、コントラストを強めて感情を揺さぶるような演出をします。広報のように「事実を伝える」だけでは購買意欲には直結しにくいからです。「欲しい」と感じてもらうためには、理屈ではなくイメージで魅力を伝える必要があります。
私が最も深く関わっていた販促では、この二つを場面によって使い分けます。
たとえば商品カタログの表紙や、商品の特長をアピールするページではイメージ画像を使います。逆に定格や仕様を説明するページでは細部まで見える商品画像が欠かせません。店頭POPや動画でも同様で、感情を動かす部分にはイメージ画像、事実を確認する部分には商品画像と、目的に応じて配置していきます。
では、この使い分けを誰が決めるのかというと、基本的には制作ディレクターです。