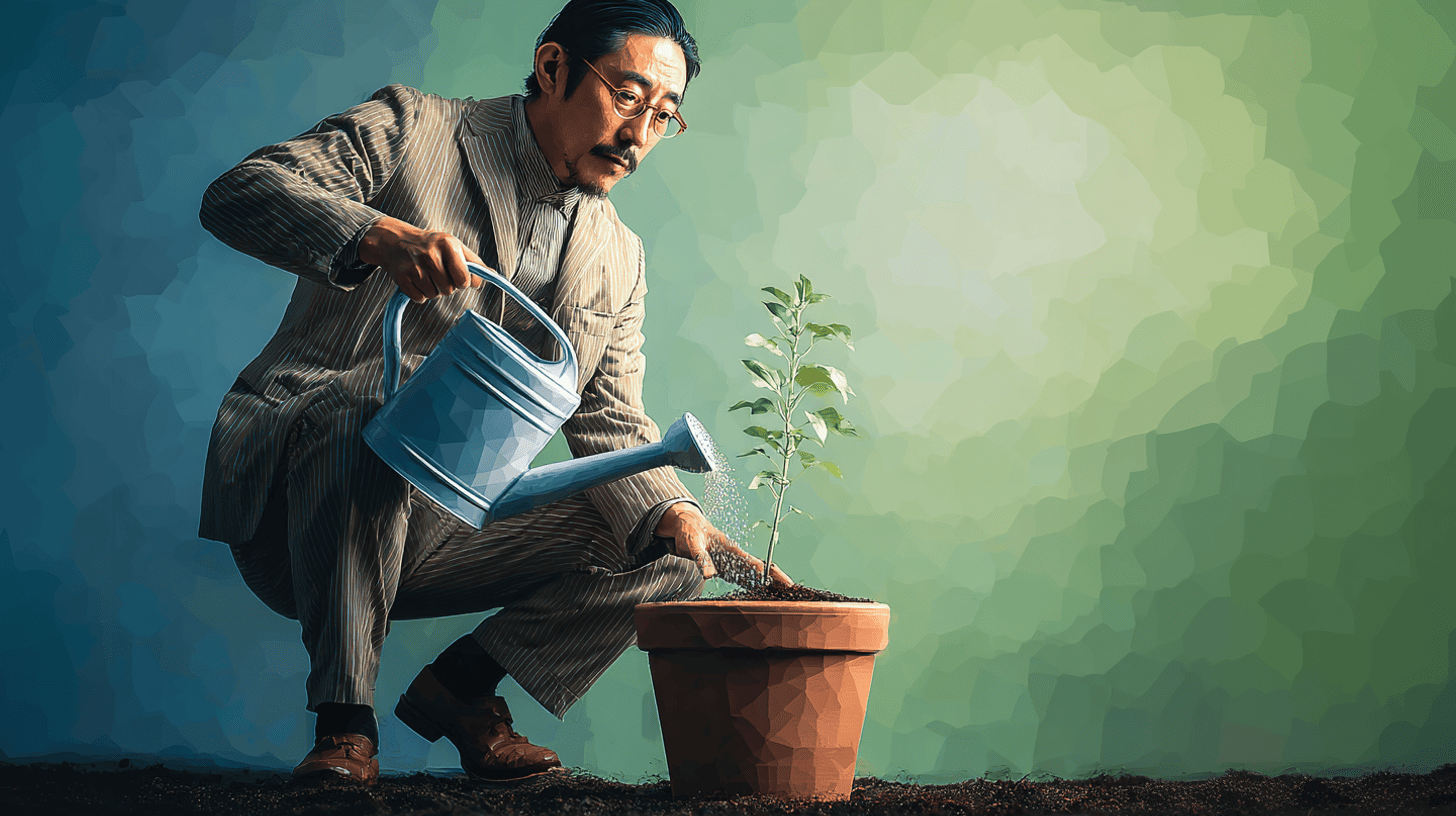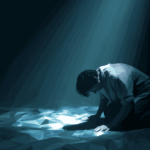子どもが生まれてからあっという間に7年が経ちました。
振り返ってみると、親として完璧な子育てをしてきたわけではありません。むしろ試行錯誤の連続で、時には後悔もありました。
それでも一貫して意識してきたこと、そして今になって「これが一番大事だった」と確信しているのは、子どもの「自立」と「好奇心」を育てることです。
子どもが小さいうちは、どうしても「親がやってあげた方が早い」「危ないからやめさせよう」と先回りしてしまいがちです。靴を履くのも、食事をするのも、片付けをするのも、こちらが手を出せばあっという間に終わります。
仕事や家事があるので待ち続けることはできません。たまに黙って待ってみると、目的からどんどん離れてたいてい遊びだします。こうなると終わりが見えなくなります。だから思わずイライラしながら「早くして!」と言ってしまうことがあります。子どもが自分でやっているのを中断させて、こちらがサッと終わらせてしまうことがあります。
でも、それでは子どもが自分で考えて動く力や最後までやり切る力が育つ機会を奪ってしまうことになります。
時間はかかっても、失敗しても、自分でやらせてみる。うまくできたときに「やった!」と喜ぶ表情を見たときに、あぁこの経験が自立につながっているんだと実感します。
また「好奇心」をどう育てるかも大切にしてきました。
子どもは本来、何にでも興味を持つ存在だと思います。葉っぱを拾って観察したり、空を見上げて「なんで雲は動くの?」と尋ねたり。親としてはつい「後でね」「今は忙しいから」と流してしまうことも少なくありません。
しかしその小さな疑問に向き合ってあげることで、「知りたい」という気持ちを大切にしているときっと伝わります。
また分からないことは一緒に調べてみることも大切です。そうすると子どもは「分からないことがあっても、自分で探せば分かる」という姿勢や行動を身につけていくでしょう。
そしてタイミングも重要だと思います。子どもが好奇心から親に声をかけてきたタイミングはまだ種の状態です。この種を逃すと次はないかもしれません。その程度の好奇心ならいらないという考えもあるでしょう。でもはじめから芽が出ていたり花が咲いていたりすることは非常に稀です。だからこそ、この種に対して時間を費やすことで芽吹かせようと促すことが大切なのだと思います。
この7年間で学んだのは、「親の価値観で子どもをコントロールしよう」とすると、子どもの可能性を狭めてしまうということです。親である自分が子どもだった時代と、娘たちが生きる現代とではさまざまな物事が変わっています。親が自分のものさしで子どもの人生を測ってはいけないのでしょう。
親ができるのは道を決めて押し付けることではありません。子どもが自分で歩いていくための土台を整えること。その土台こそが「自立」と「好奇心」だと思うのです。
自分のことを自分でできる力があれば、挑戦を恐れずに進んでいけます。そして好奇心があれば、世界はもっと広がっていきます。
もちろん、まだ7年しか経っていません。これから思春期を迎え、さらに複雑な関わりが必要になるでしょう。それでも、「自立」と「好奇心」という軸を忘れずに関わっていけば、どんな壁に直面しても一緒に乗り越えていけるはず。もしくは「誤りでした」という内容の土下座記事を投稿するかもしれません。