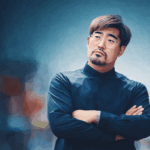私にはふたりの姉妹の娘がいます。これまで長女のことはいろいろ書いてきました。特にいじめ被害とその後遺症について。また発達障害についても少しだけ触れました。
長女は言語能力に秀でているので大人のいうことへの理解が高いのですが、それに沿った行動をしようとしてもまだ発達段階なのでうまくできないというジレンマを抱えています。また感覚過敏なので、イヤーマフを使ったり味覚や食感が敏感だったりします。自他境界があいまいなのでよく言えば共感力が非常に高いです。悪く言えば他者への依存度が高いです。
それに引き換え、次女にはそうした様子はあまり見られませんでした。心療内科の先生からは姉妹ということや生活環境の要因から発症しやすいと思うと言われていました。
それでも今のところ素人目には長女とは違って発達障害ではないように感じます。
ですが、そんな次女も保育園で問題を抱えることになりました。発端は1歳児クラスのときなのですが、同じクラスの女の子に腕を噛まれました。また同じクラスの男の子には頬を噛まれました。女の子に噛まれた腕にはクッキリと歯形がついていました。その日の入浴中に透明なジェルのようなものが傷口から出ていました。ネットで調べたところ、細菌に対抗するための免疫なのだそうです。
1歳なのでそういうこともありえると思いました。また反対に噛んでしまうことも起こりうると思いました。運よく変な感染症などにはならなかったので、特に大きな問題にはしませんでした。
おかしいなと感じたのはしばらくしてからです。
就寝時にベッドに入り、寝るまでに30分〜1時間かかるのが次女の普通です。その寝かしつけをしていると何度も噛まれたことを訴えてきます。2歳児クラスに上がってからは、なんで噛まれたんだろう?という意味のことを言うようになりました。
1歳のことだったので、時間とともに痛みも忘れていくだろうとタカを括っていました。ですが違いました。日に日にその痛みの記憶が強くなり、そして噛まれた理由まで思い悩む事態になったのです。
そうすると次女の立場で考える必要が高まります。噛んできた恐怖の対象である女の子と男の子が同じクラスなので、一日中行動を共にします。つまり恐怖と隣り合わせということです。
この状態は長女のときと似ています。もしかすると長女と同じように登園できなくなるのではないかと想像していました。
案の定、登園できなくなりました。2歳児クラスになってすぐでした。
早朝に登園すると部屋には誰もいないので、駆け足で部屋に入ります。そして楽しそうに部屋中を走り回る姿を見ることができます。いたって元気で明るく子どもらしい印象です。
ですが少し登園時間が遅れると、他の子どもはすでに登園しているので部屋で遊んでいます。もちろん噛んだ女の子と男の子もいます。
そんな日は部屋に入らずに、急に手を洗いたいと言い出して手洗い場へ向かいます。止めようとしても抵抗します。そして5回でも6回でも手に泡をつけて洗い流してはまた手に泡をつけます。このくり返しです。次女なりの心の準備なのかと見守るようにしていましたが、いつも本当に止まらないのです。なので無理矢理止めて部屋へ連れて行こうとします。すると大泣きです。
そんな状態が1か月弱続いたかと思うと、今度は入り口で立ち止まり、ドアのふちの影に隠れつつしがみついて部屋に入ろうとしなくなりました。それどころか帰りたいと言い出します。手を洗いにいくことさえしません。
次女にとって噛まれたのは完全にトラウマです。保育園にいくことは恐怖の毎日だったでしょう。
長女のときの保育園の対応をふり返ると、次女にとって安心できる環境づくりをしてくれることはないと思いました。なので妻と話し合って転園することを決めました。この転園を機にまた園に楽しく通えるようになるといいのですが。
長女につづき次女も被害者です。姉妹そろって誰にも暴言や暴力を振るっていないことを考えるとあまりに不条理です。不運だなと思ったりもしました。
ですが最近は逆に運が良かったと思うようになってきました。心に傷を負ったことは悔やまれますが、そのぶん他者へ優しくできる人になれるだろうと思います。
それとこれまでの社会のように保育園や教育機関へ通って当たり前という既定路線から外れたことで、私たち夫婦がこれからの時代を見据えて育児・教育して行こうと考え方をシフトできたことが大きいです。長女は小学校に通えていません。だから別の生き方を模索し出しています。次女についても同じ考えのもとで育てていこうと思います。
この固定観念から考え方をシフトすることについては別記事で書きたいと思います。