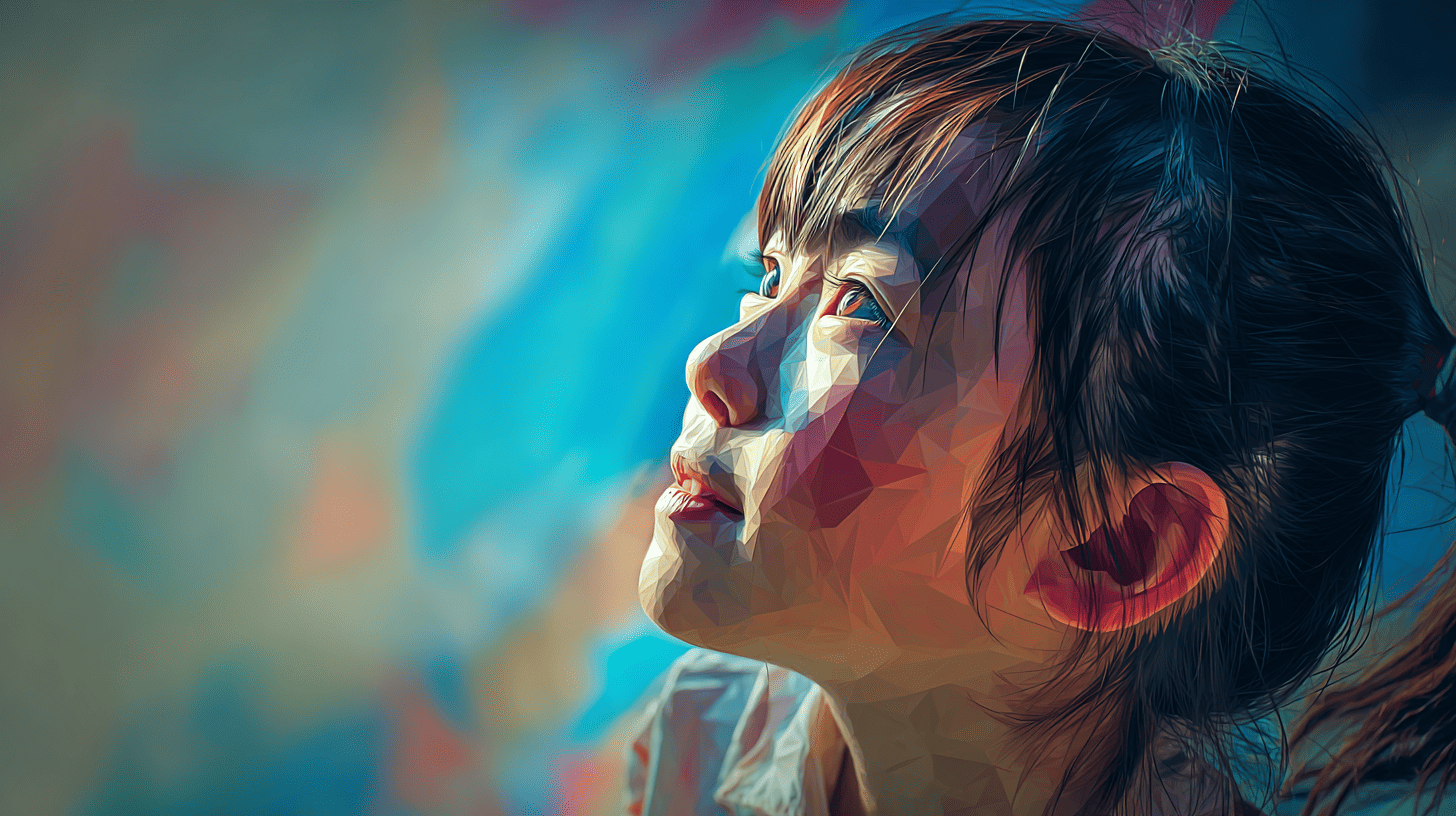わが家の長女はいま不登校です。その原因をひとつに特定することは難しいですが、最大の要因は保育園時代のいじめ被害にあったのではないかと思います。
陰湿で狡猾ないじめを4歳クラスか5歳クラスのころから受けていたようです。ほぼ毎日のように暴言や暴力を受けていたと後から聞きました。しかも驚くことに、保育園側は被害者である娘に寄り添うのではなく、加害児童をむしろ褒めていたのです。当然のように不登園になりました。
そして卒園式では、その加害児童が娘の隣に配置されてしまいました。そのため娘は卒園式を欠席しました。いま思い返しても、娘にとってあの空間は安心できる場所ではなかったのだろうと思います。
こうして集団生活そのものに強い不安や恐怖を抱え、不登校のきっかけをつくってしまったのです。
小学校進学のタイミングでは、支援級に通うことにしました。支援級は、いわゆる普通級のようにスムーズに登校できる子どもたちではなく、いろいろな理由で学校生活に困難を抱えている子どものためのクラスです。最初は娘もそこへ通ってみました。先生方も子どもの特性やペースに寄り添いながら、柔軟に対応してくれる雰囲気がありました。ここなら大丈夫かもしれないと感じたのも束の間、2週間ほどで行けなくなりました。
結局、自宅学習でやっていくしかない状況になっています。幸いなことに、私は自宅で主夫業をしていました。妻もフルリモートで働いてくれています。親がそばにいて支えながら学べる環境は整えられています。生活のバランスを保ちながら、娘の学びを続けることができています。
この経験を通じて感じたのは、文部科学省の学習要領に沿って、苦手な集団生活に無理に合わせて毎日を過ごす必要性は本当にあるのだろうか、という疑問です。
苦手なことに挑戦して乗り越える経験は大切です。しかし、そもそも通学が困難な子どもにとって、学校という環境の中でその力をつける必要があるのかどうか。私は必ずしもそうではないと思うようになりました。
むしろ、得意な分野や環境があるなら、そこで経験を積んだり力を育んだりすればいい。そこにこそ子どもが自信を持ち、学び続ける力を養えるのではないかと考えています。
改めて学校とは何かを考えると、同じ教師が多数の子どもたちに対して、同じ内容を一斉に教える場所です。教育要領に沿って画一的に進められる授業。加えて学校ごとの校則や教師の意見に従うことが当然とされます。その延長線上にあるのは、大企業や組織の中で上司や社長の命令に従って動く人材の育成です。
高度経済成長期には、この仕組みで「平均的でそつのない人材」を大量に育てることが社会にとって合理的だったのかもしれません。しかし、いまは100年近く時代が進んでいます。求められているのは、変化に柔軟に対応できる人です。
だからこそ、学校に求めるものは「得意や好奇心を伸ばせる環境」であるべきだと私は思います。子どもの得意を見つけ、それをさらに伸ばす。好奇心を丁寧に観察し、深掘りしたり幅を広げたりして、専門性を高めたり選択肢を増やしたりする。これが教育の核になるべきだと思うのです。
苦手を無理に克服することが第一ではなく、得意や好奇心を通じて学びを広げていく。その方が子どもは前向きに学び続けられるのではないでしょうか。
個別的な教育を受けた子どもは、平均から外れた「偏りのある人物」になるかもしれません。しかしその偏りこそが、これからの社会で価値を持つのだと思います。
AIが人間の知識や技術を超えるのはすぐそこだと言われています。今日役立つ知識が明日には古くなる時代です。そんな社会では、平均的な人物でいるよりも、自分の得意や好奇心を武器にして学び続けられる人物の方が強い。私はそう確信しています。
だからこそ、娘の不登校という経験は私たち家族にとって辛いことでしたが、そのおかげで「学校に求めるものは何か」という問いにたどり着けました。
答えはひとつではありませんが、少なくとも私にとっては「得意や好奇心を伸ばすこと」「学び続ける姿勢を支えること」だと思っています。
不登校は社会的にはネガティブに見られることが多いですが、そこからしか見えない景色があるのも事実です。子どもにとって最適な学びの形を探すことは、親としても社会人としても大切な問いかけなのではないかと思います。